河川堤防の合理的な植生管理・生態緑化手法の開発
”山田 晋 先生
農学部 生物資源開発学科
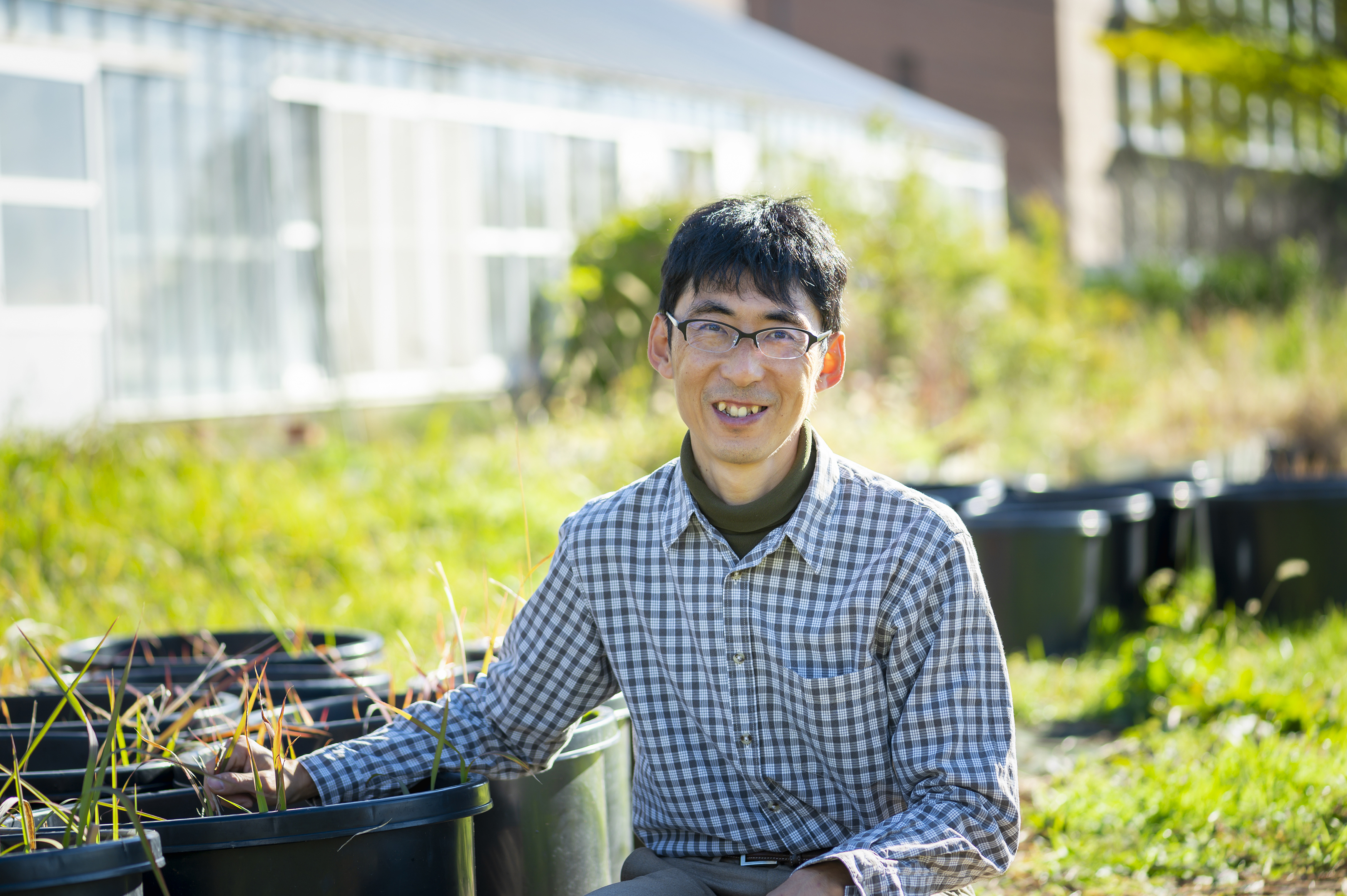
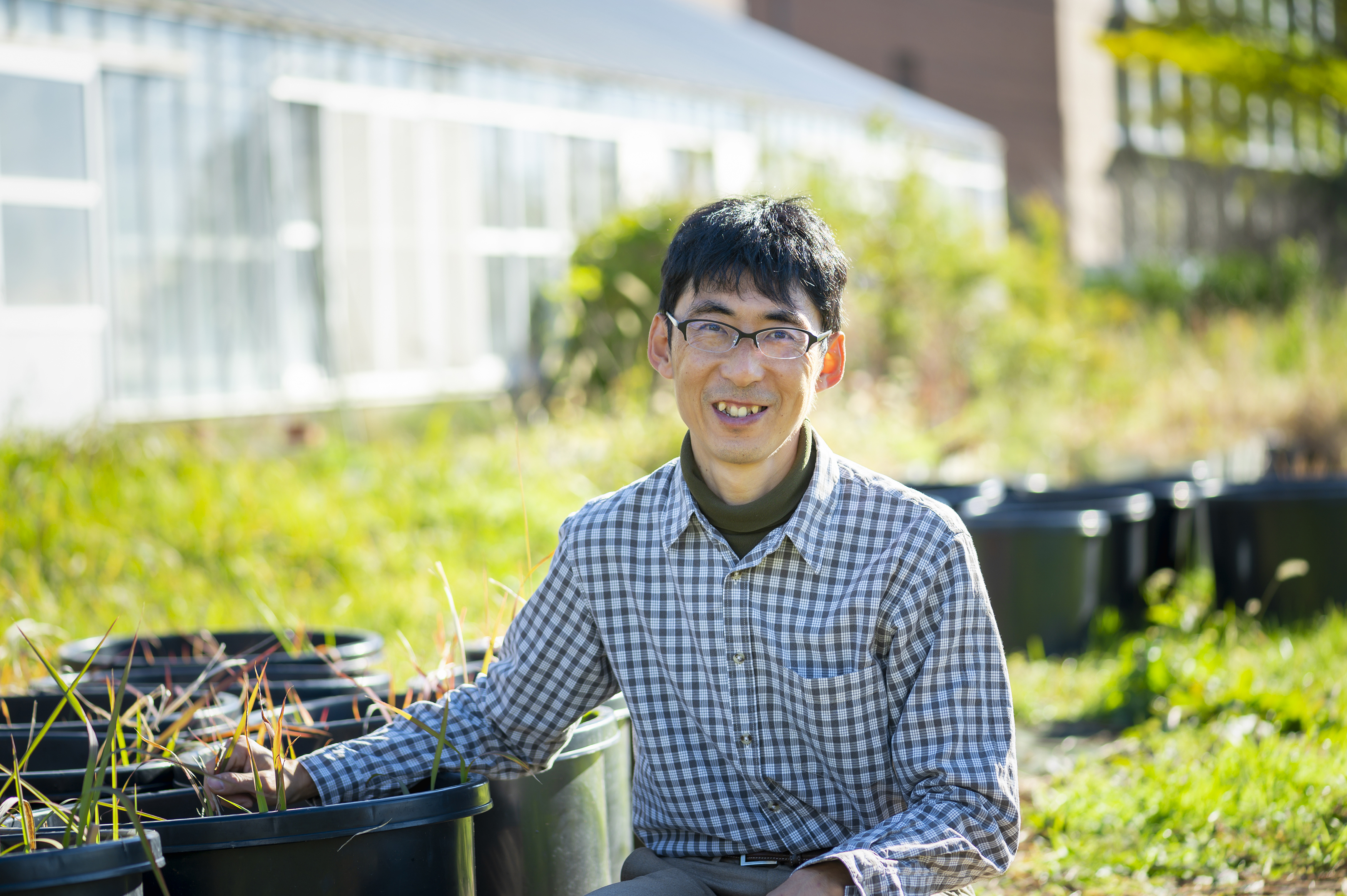
山田 晋 先生
農学部 生物資源開発学科
”河川堤防の合理的な植生管理・生態緑化手法の開発
”河川堤防の合理的な植生管理・生態緑化手法の開発
”農学部 生物資源開発学科
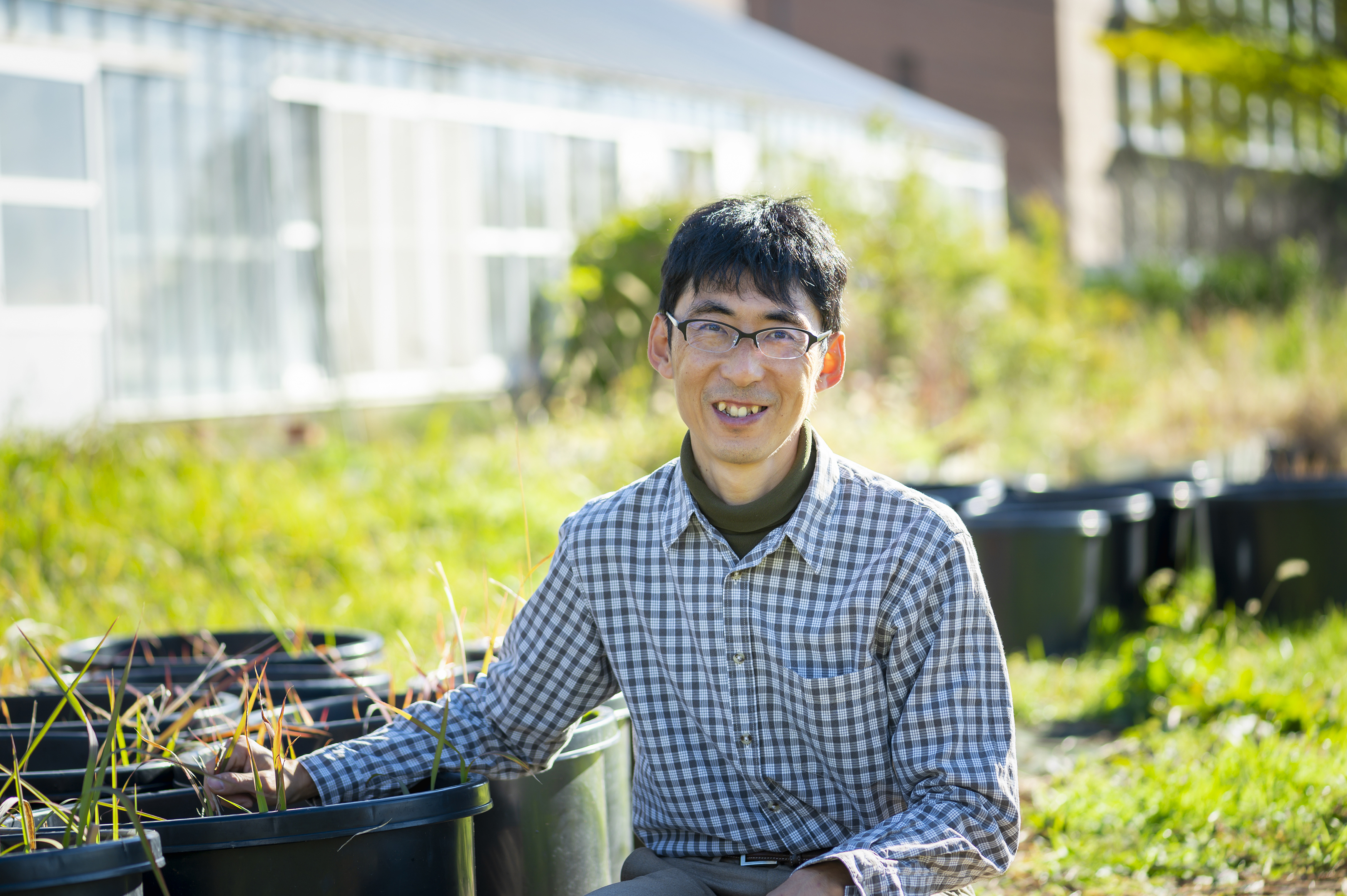
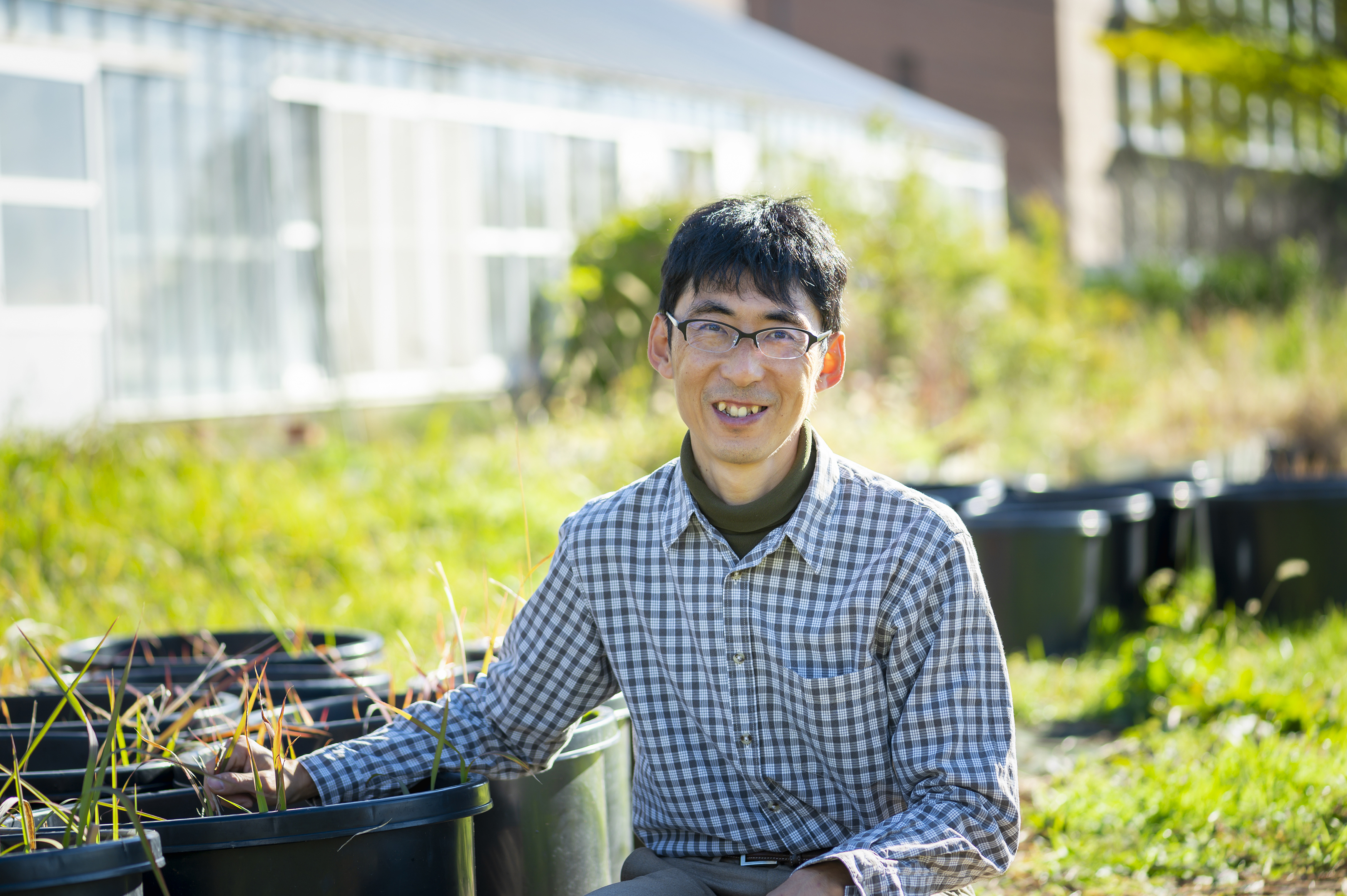
農学部 生物資源開発学科
”河川堤防の合理的な植生管理・生態緑化手法の開発
”
研究を始めるよりずっと前から、川の堤防をよく見ていると、セイタカアワダチソウと呼ばれる外来種が繁茂していて、河原や河川敷が黄色になっているところが非常に多いことが気になっていました。堤防にはオミナエシやカワラナデシコなど絶滅危惧種植物が生育する場所もあるのですが、その見た目は2つの場所間で明らかに大きく違います。
現在、国土強靭化事業の一環として、より大規模な、洪水に耐え得る堤防への拡幅工事が各地で進んでおり、古い堤防はしばしば土盛りして新しい堤防に作り替えられます。元来そこに生育していた絶滅危惧種植物は埋まって姿を消してしまい、新しい堤防でそれらが新たに生育されることはまずありません。しかし、古い堤防もその多くは元来人工物だったはず。であれば、新しい堤防で珍しい植物が生育するようにはできないだろうかと考えたことが、現在取り組んでいる研究のきっかけです。
河川管理者は植物の生育特性に精通しているわけではないため、植生まで考慮した上で堤防を作ったり管理してはいないのです。そこで私たちが貢献できる余地があると感じ、日々研究を続けています。
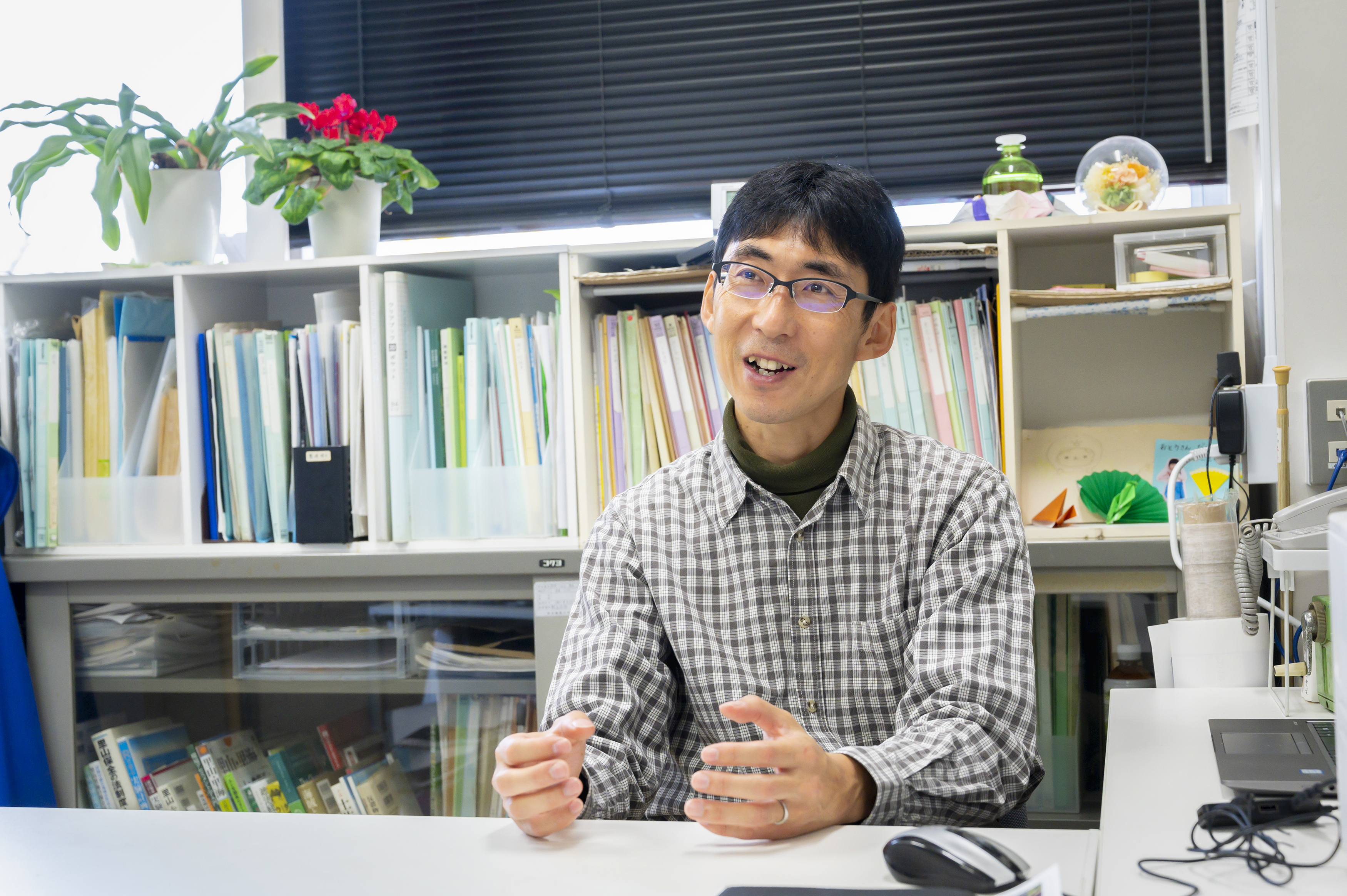
河川堤防は国土保全上重要な施設です。堤防植生には、洪水や氾濫による被害を防ぐための耐侵食機能や、堤防の破損が見つけやすい=視認性などの治水機能が求められるのですが、維持管理予算の縮減に伴い、かつて維持されていたシバ草地を高頻度で管理することが困難となっています。
管理の粗放化に伴って、シバより耐侵食機能や視認機能が低下する高茎草本群落に置き換わった箇所も多くあります。新たな管理体系に基づく植生管理が求められているものの、適切な方法がまだ見つかっていないため、堤防管理上望ましいとは言い難い植生になっている事態も散見されています。
近年、耐侵食機能や視認性の点でシバに次ぐ機能を持つとされるチガヤという植物が注目されるようになりました。治水機能が低い外来植物が繁茂する堤防にチガヤが繁茂するように、河川堤防を管理上望ましい植生に誘導するための植生管理手法を考案することが現在の私の研究テーマです。川の堤防はもちろん、圃場でも、ここ厚木キャンパスでも様々な実験を試みています。従来の管理コストを逸脱しない範囲での管理手法を開発し、堤防の持つ治水機能を高めることで、住み続けられるまちづくりを支えていければと考えています。
気候や気象は毎年同じことの繰り返しではなく、ある時は秋がとても暖かいとか、短いといったことがあります。その結果、草の生え方が予想とずれていた!など思い通りにならないことの方が少なくありません。また、植栽してそれで終わり、ではなく植物が落ち着く、定着するのに少なくとも3~5年かかることを加味して、常に2段階、3段階くらいで実験の計画を立てているのが現状です。とても労力はかかりますが、予想通りにはならなくても簡単には実験を失敗させないように計画を練ることが研究者としての腕の見せ所かもしれません。
私の研究によって堤防の治水機能が向上すれば、堤防の決壊頻度が低下し、都市生活における安全性が高まることにも寄与できると考えています。また、チガヤを用いた植生管理手法が一般的になれば、春の花粉症の原因植物の一つである外来牧草ネズミムギの量を堤防から減らせる可能性があります。そうすると全国の花粉症に悩む方々に喜んでもらえるかもしれません。
世界中を見渡しても、実は堤防での植生に関する研究はとても事例が少ないのです。たとえば欧州では雪解けによって川の水位が増えていきますが、日本では豪雨による一気の洪水が多いので、気候条件なども加味して、日本は日本国内での事例を蓄積していく必要があるなと感じています。
私自身も植物が好きで研究に携わっていますが、こんなにも知らないことだらけなんだ、と気づかされる毎日です。自然への理解が深まっていくことは自分自身のやり甲斐でもありありますし、社会に与えるインパクトも大きく、人の役に立つ分野だと思っています。大人から子どもまで、みんなが自然とうまく付き合える、自然の発するメッセージを受け止められる社会になれば理想的ですね。
千葉県柏市にある利根川の堤防は在来種であるウマノアシガタが生える場所です。
フィールドワークの植生調査で分からない植物種があると、サンプルを持ち帰り図鑑や実態顕微鏡を使って植物種名を同定します。

研究のメインはフィールドワーク。河川堤防はもちろんのこと、厚木のキャンパスでも実践しています。

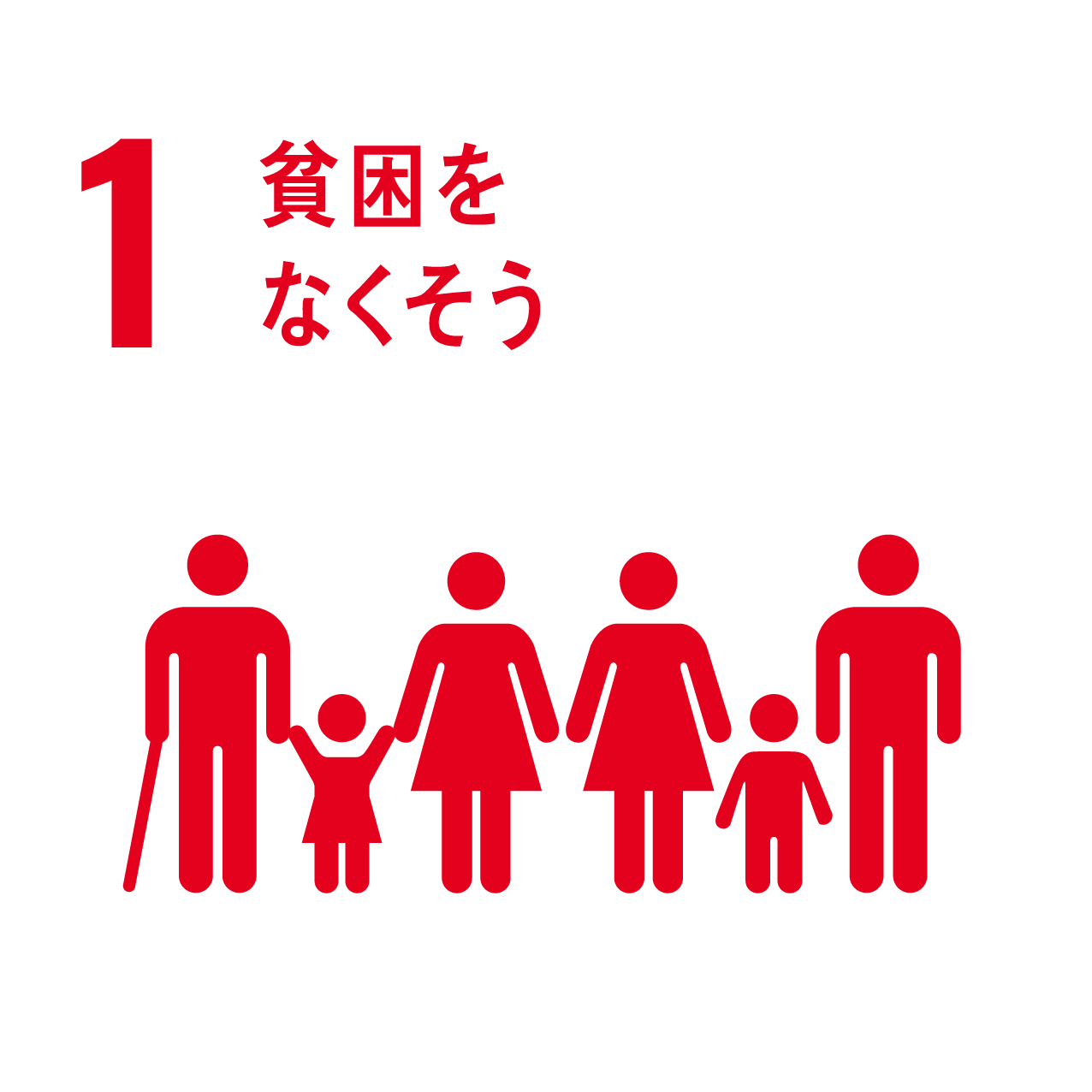
「貧困をなくそう」
杉原 たまえ 先生
国際食料情報学部
国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」
松田 浩敬 先生
農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」
勝間田 真一 先生
応用生物科学部 栄養科学科
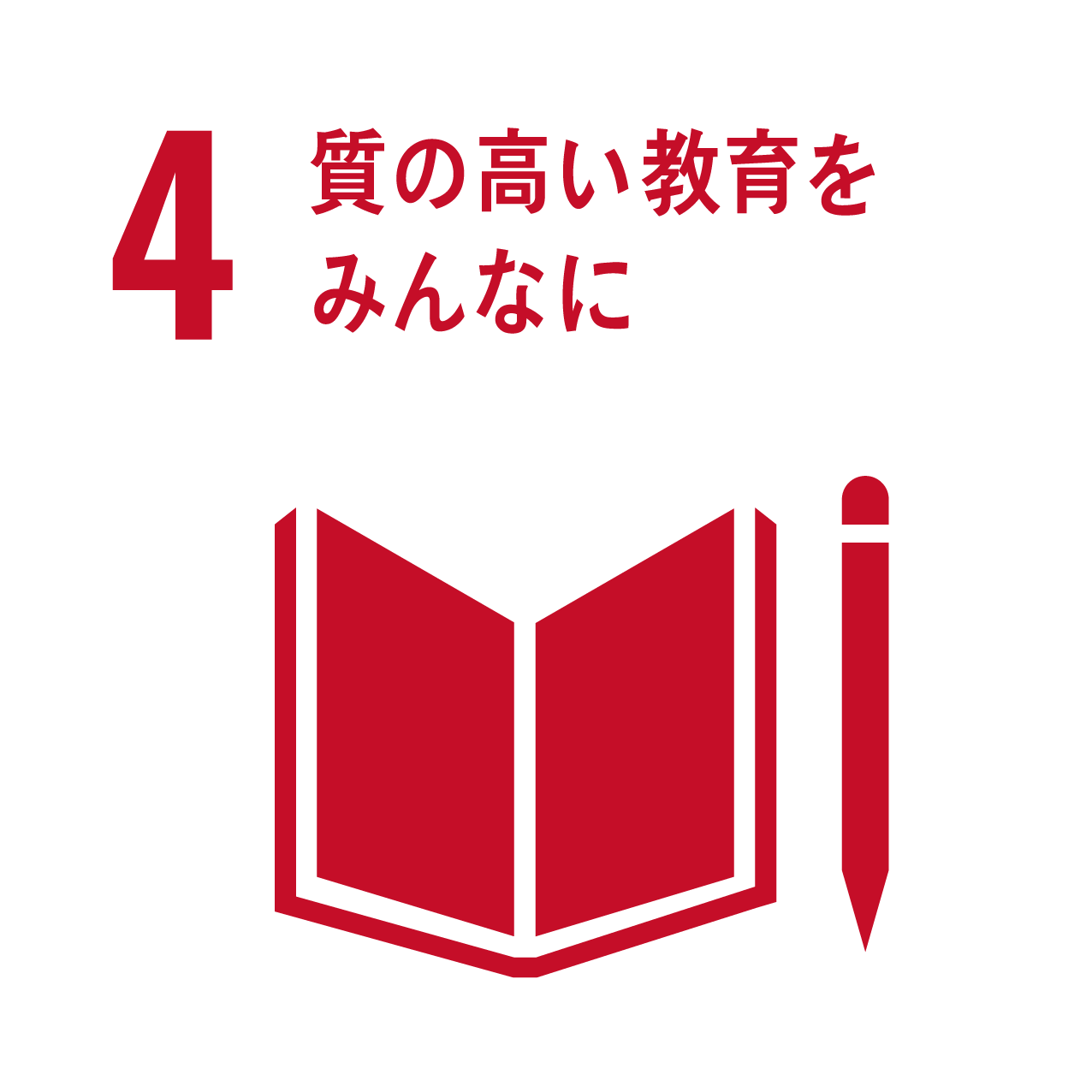
「質の高い教育をみんなに」
武田 晃治 先生
教職課程
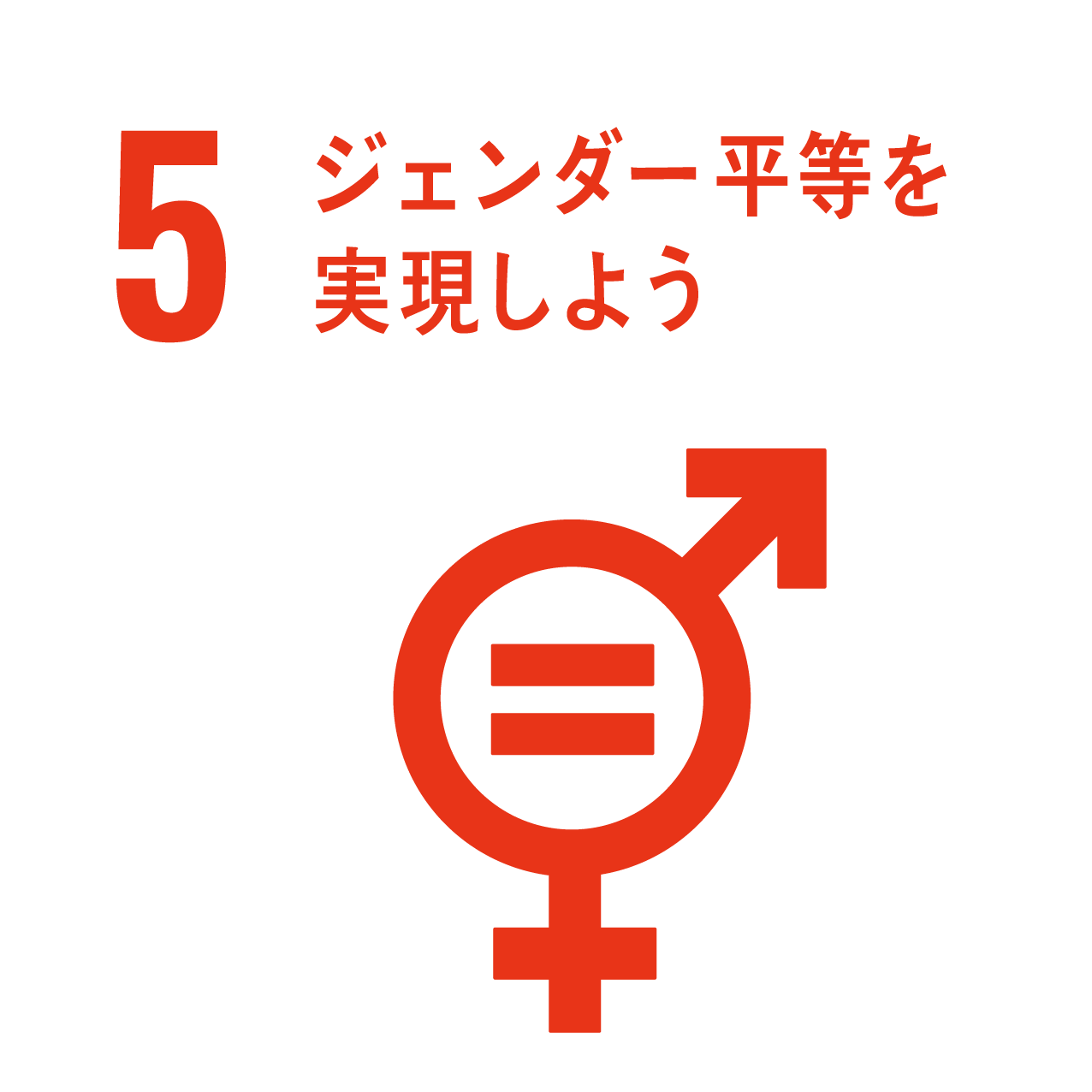
「ジェンダー平等を実現しよう」
原 珠里 先生
国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」
藤本 尚志 先生
応用生物科学部 醸造科学科
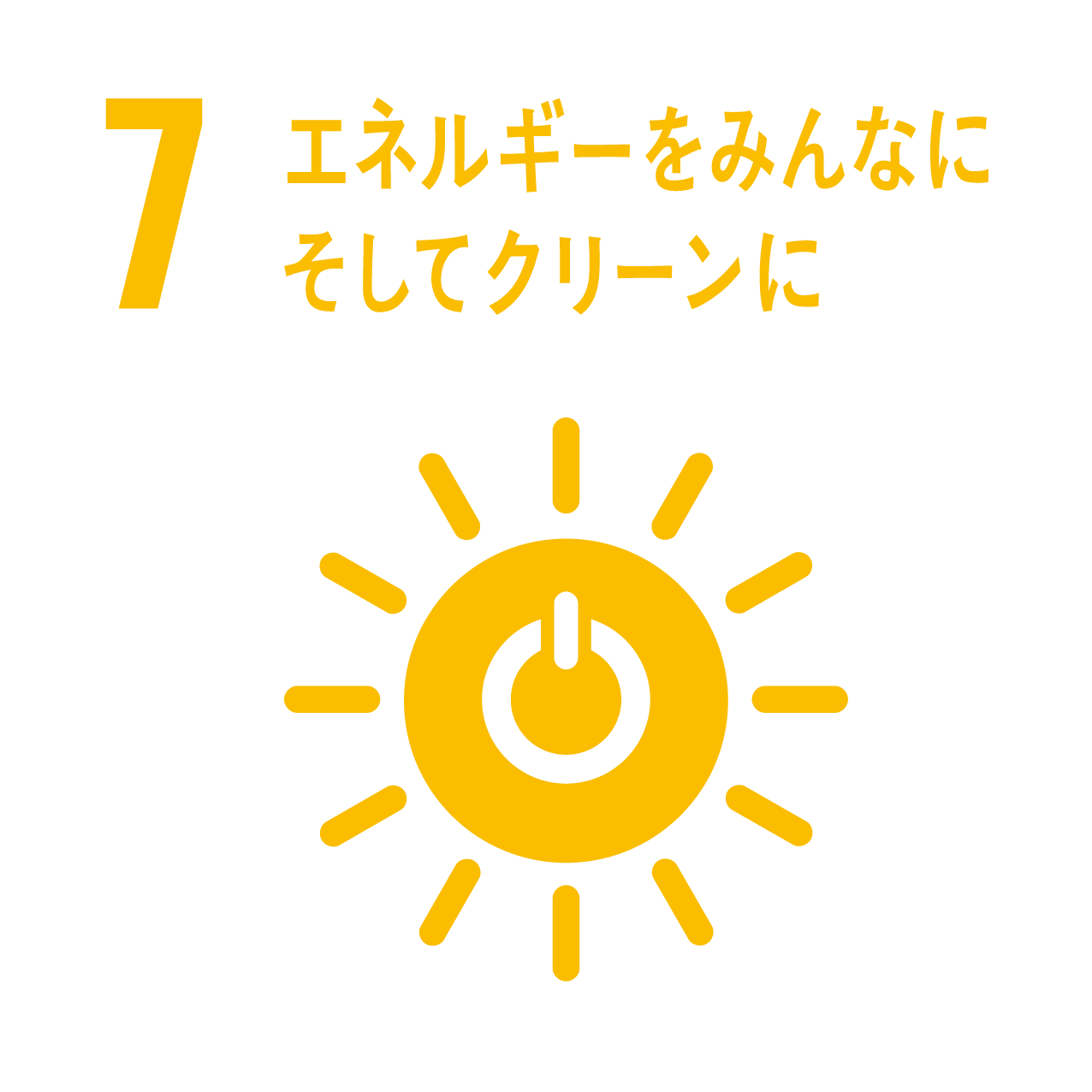
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
トウ ナロン 先生
地域環境科学部 生産環境工学科
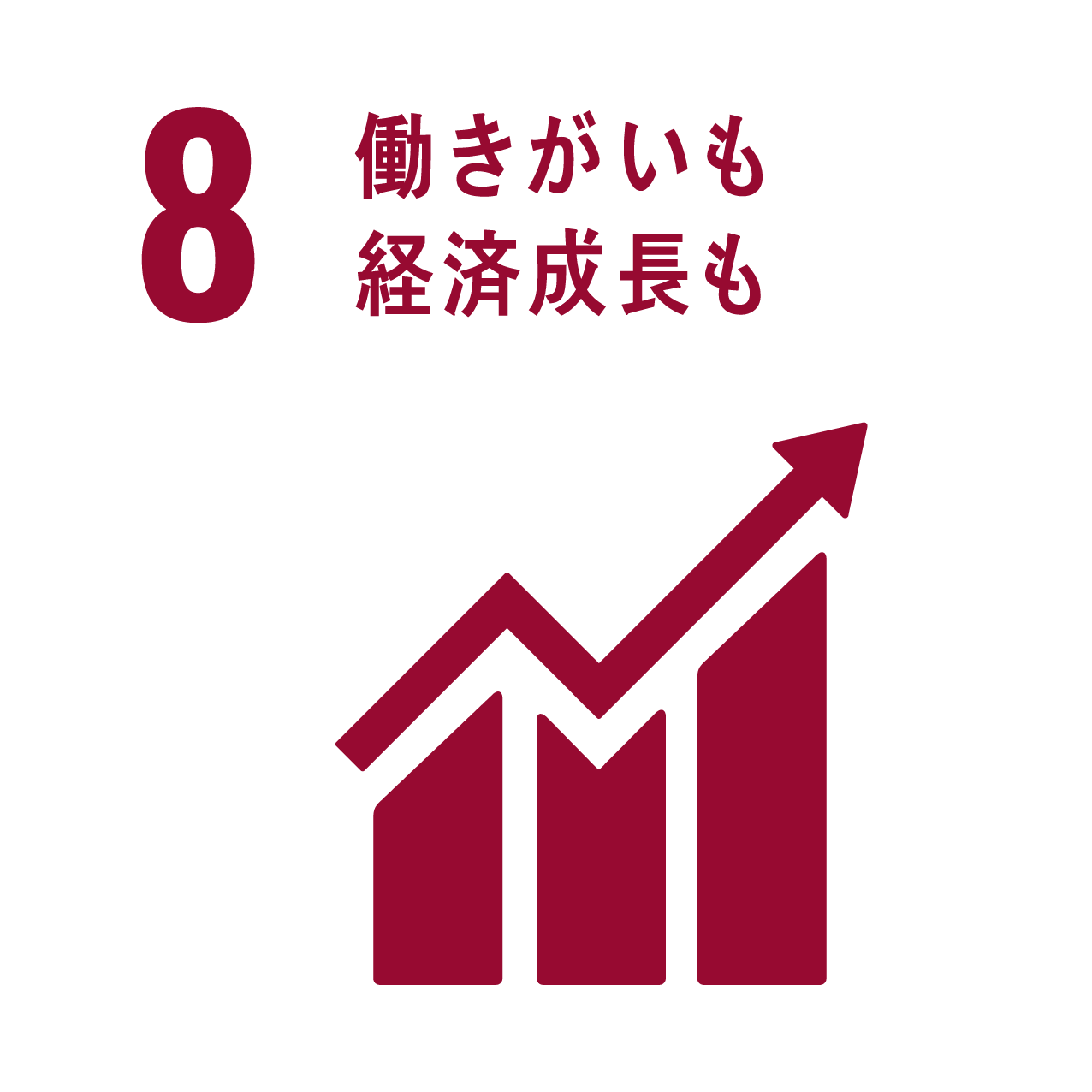
「働きがいも経済成長も」
寺野 梨香 先生
国際食料情報学部 アグリビジネス学科
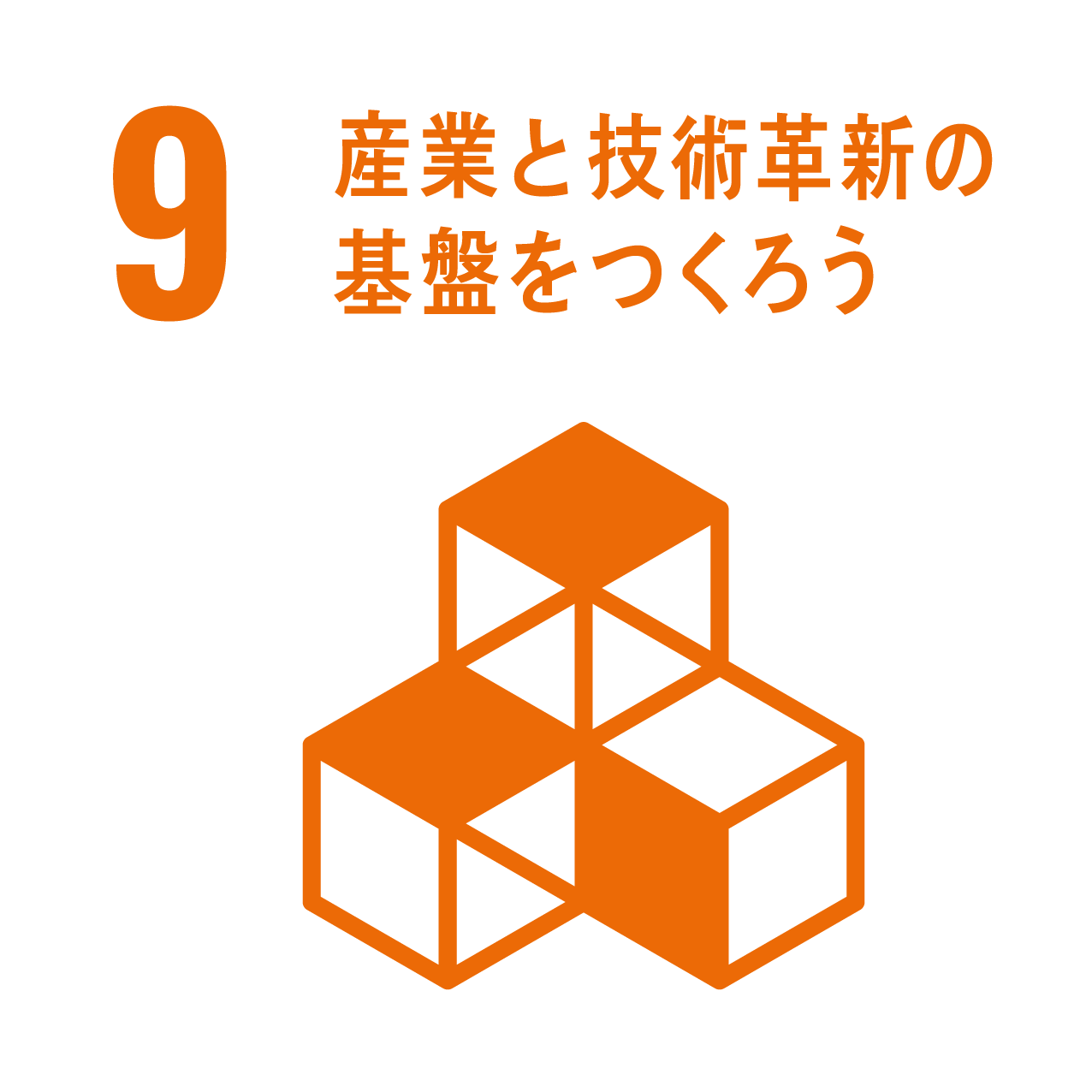
「産業と技術革新の基盤をつくろう」
石井 大輔 先生
生命科学部 分子生命化学科
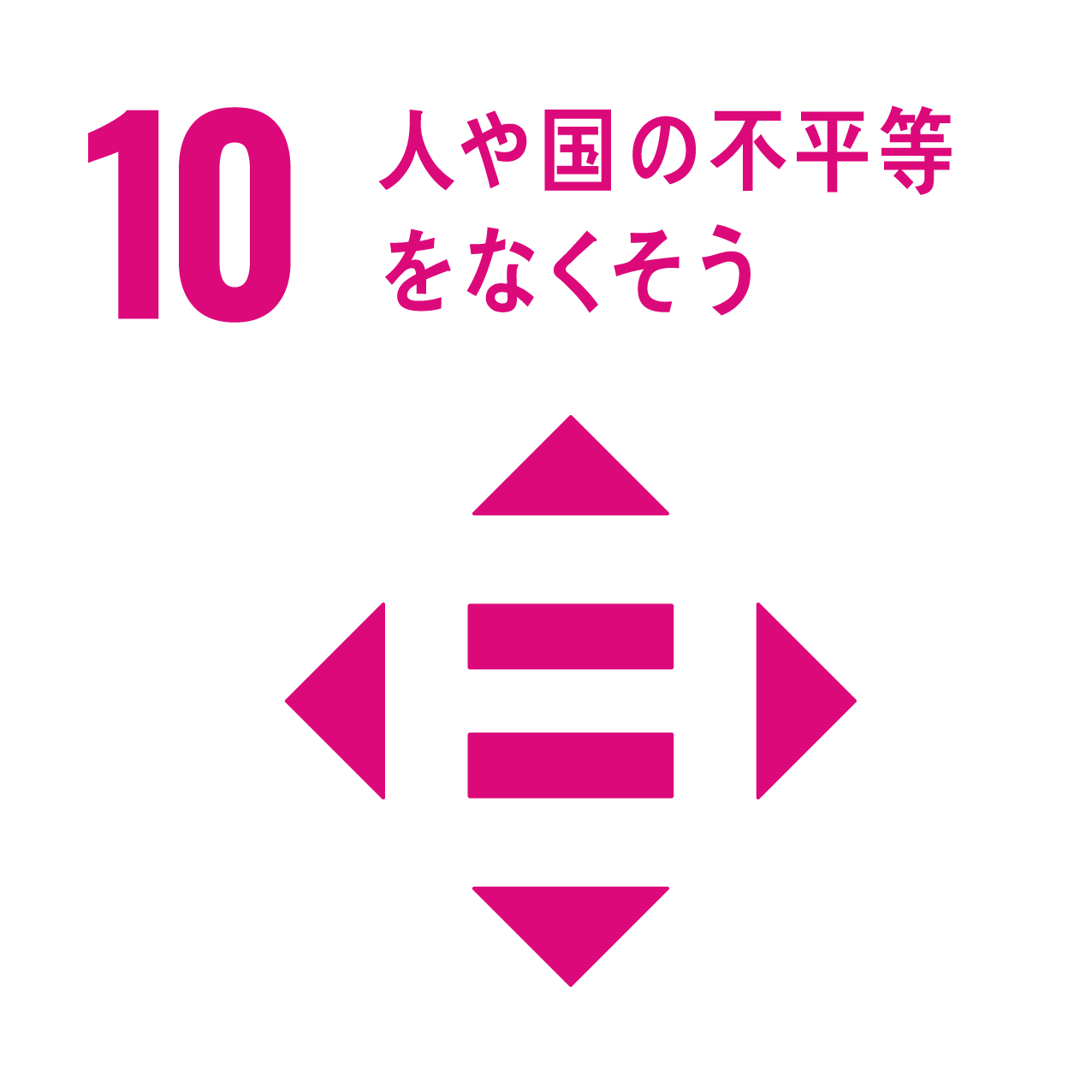
「人や国の不平等をなくそう」
五野 日路子 先生
国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」
山田 晋 先生
農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」
野々村 真希 先生
国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」
太治 輝昭 先生
生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」
中川至純 先生
生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」
入江 彰昭 先生
地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」
佐藤史郎先生
生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」
増田 宏司 先生
農学部 動物科学科