マレーシア稲作地帯における持続可能な稲作経営と生産工程
”寺野 梨香 先生
国際食料情報学部 アグリビジネス学科


寺野 梨香 先生
国際食料情報学部 アグリビジネス学科
”マレーシア稲作地帯における持続可能な稲作経営と生産工程
”マレーシア稲作地帯における持続可能な稲作経営と生産工程
”国際食料情報学部 アグリビジネス学科


国際食料情報学部 アグリビジネス学科
”マレーシア稲作地帯における持続可能な稲作経営と生産工程
”
卒業論文で東南アジア5か国の稲作生産構造について調べ、マレーシアの稲作農業に興味を持って以来、大学院に進みマレーシアの稲作生産および経営について調査研究を続けています。大学院1年の時に、マレー農村に長期滞在しながらフィールドワークを行うスタイルで農村調査研究を行ったのですが、英語が公用語になっているマレーシアでも農村の皆さんとはマレー語でコミュニケーションする必要があります。農家さんを1軒1軒回って、どのような農業を営んでいるか調査して、経営分析をしながら、同時にマレー語も鍛えてもらいました。
マレーシアには東京農大の姉妹校留学制度を使って渡航したのですが、留学先はアグリビジネスマーケティングや経営についての研究も盛んな大学でした。イスラム教国ですから、たとえば消費行動論を学ぼうとするとムスリムの研究も必要になります。生産者側、消費者側、双方について学べたのは貴重な経験でした。また異教徒で外国人の私を研究チームに引き入れてくれて、コミュニティに歓迎してくれるマレーシアの人たちの懐の深さに大きく惹かれたことも、研究を続けてこられた一端となっているかもしれません。
現在は、稲作経営や農家経営に関する調査に加え、農民の意識調査や、そして当時の農業や、その作業工程の現状を調査し、独自にサステイナブル指標を構築して農家ごとの農業経営や稲作の作業工程について研究をしています。
マレーシアでは食・農・環境に関わる認証制度のMyGAP(マイギャップ)が2013年からスタートしました。MyGAPは生産工程を管理するもので、化学肥料や農薬の使用量が規定に沿っているかに加えて、生産者がグローブやマスクを着用して衛生管理に配慮しているかなどが認証の基準となるものです。近年、マレーシアの稲作においてもサステイナブルという言葉はキーワードになりつつあるのですが、普及の実態はまだまだというところです。認証取得の有無に関わらず、農薬の散布に対する意識などが、農家ごとに様々であることも課題の1つです。
マレーシアは若い人が非常に多い国ですが、東南アジアの中では課題先進国と呼ばれており、近年は農業従事者の高齢加や後継者不足、進学率の上昇で農村から都市部へ移る若い世代が多いなどの理由から一部の地域で農業離れが起きています。たとえ生産量や多く単収が高くても、抱える課題によっては離農してしまう農家さんもいます。投入剤や農薬の散布量に配慮しない農業に比べると、MyGAPのような認証制度に申請するなど、持続可能な農業を目指すのはとても手間がかかります。特に今は現地に行って調査ができないので、オンラインインタビューや現地の共同研究者とどこまで課題そのものを見つけられるかも新たな課題として浮上している状況です。ですが、この研究が情報共有やノウハウの蓄積への一助になればと思っていますし、タイやインドネシアのような近隣諸国が同じ問題に直面したときに応用できるのではないかと期待しています。

農業離れという実情はあるものの、国は耕作放棄地でグループファーミングを行うなどの政策も推進していますし、農業の良さや農家になることを推進するだけでなく、食や農でアントレプレナーを目指すとか、農業に対して前向きなビジョンを持つ人が多いことにポテンシャルの高さを感じています。
私もメインの研究と並行して現在取り組んでいるのが、インバウンドのムスリム対応です。今、日本各地の農村でマレーシアなどからの訪日客へのおもてなしを工夫しようという流れがあり、皆さん素晴らしい努力をされているところに私も事例研究や論文のまとめなどで関わらせてもらっています。最近はマレーシアやインドネシアの大学からウェビナーの機会をいただいて、あちらの学生さんに講義をすることもありますし、日本の農業に興味を持っている学生さんとの出会いもありました。農村の方や私たちからマレーシアへ良い影響を与えられることはとても励みになるし、これからも活発な交流や情報交換を続けていければと思います。変化が生じたときに、柔軟に受け入れる力や適応する力が持続可能な農業やSDGsの時代に求められているものなのかもしれません。
学生たちがSDGsについて熱心に向き合っている様子は、自分も農大での学びに夢中だった日々を思い出させてくれます。

調査を行っていたペナン州北部の稲作地帯。農家を1軒1軒回りました。
日本の農家さんが農泊事業のためにムスリム対応を考えたり、日本の農業に関心を持つマレーシアの学生がいたり。絶え間ない交流や情報交換が研究の後押しになっています。

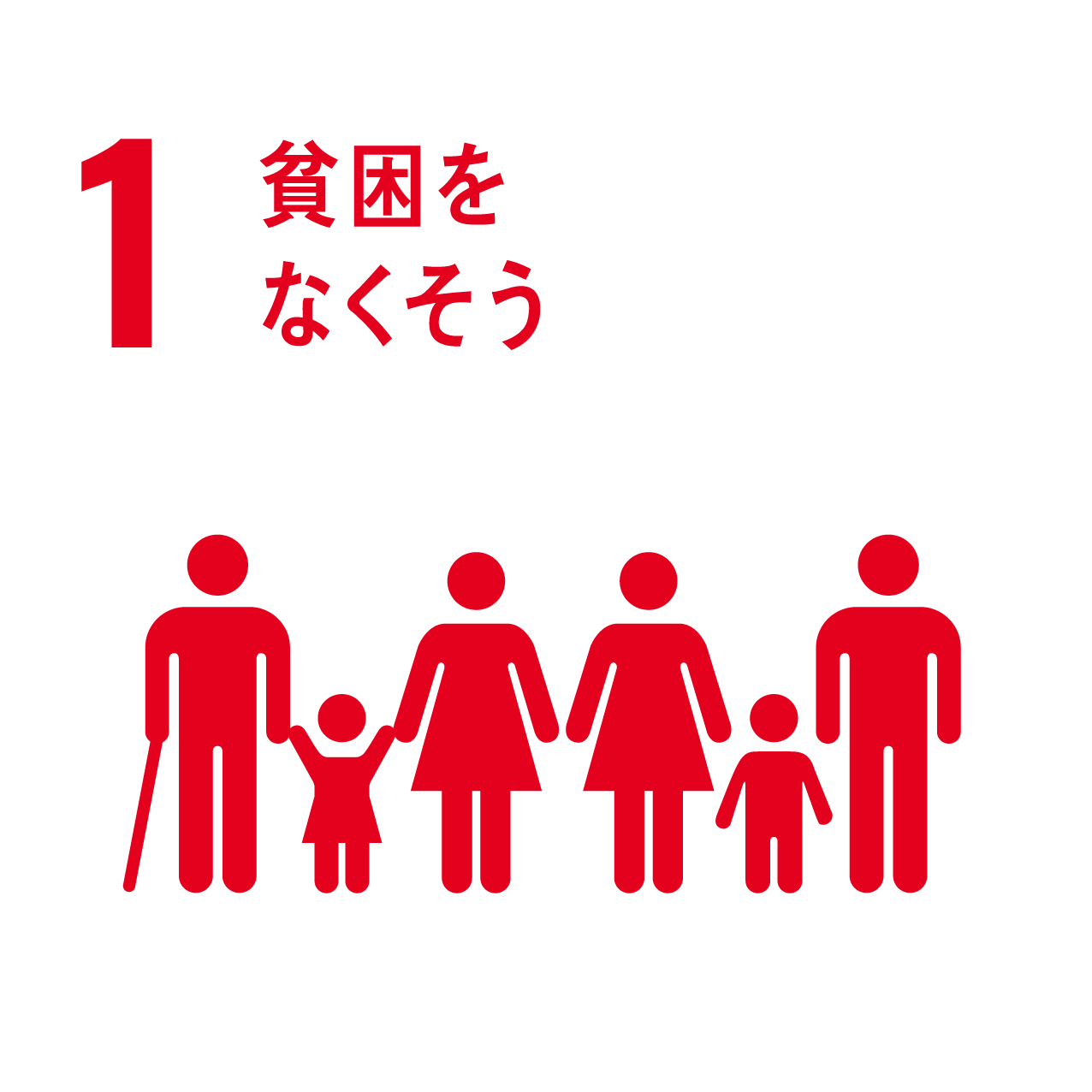
「貧困をなくそう」
杉原 たまえ 先生
国際食料情報学部
国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」
松田 浩敬 先生
農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」
勝間田 真一 先生
応用生物科学部 栄養科学科
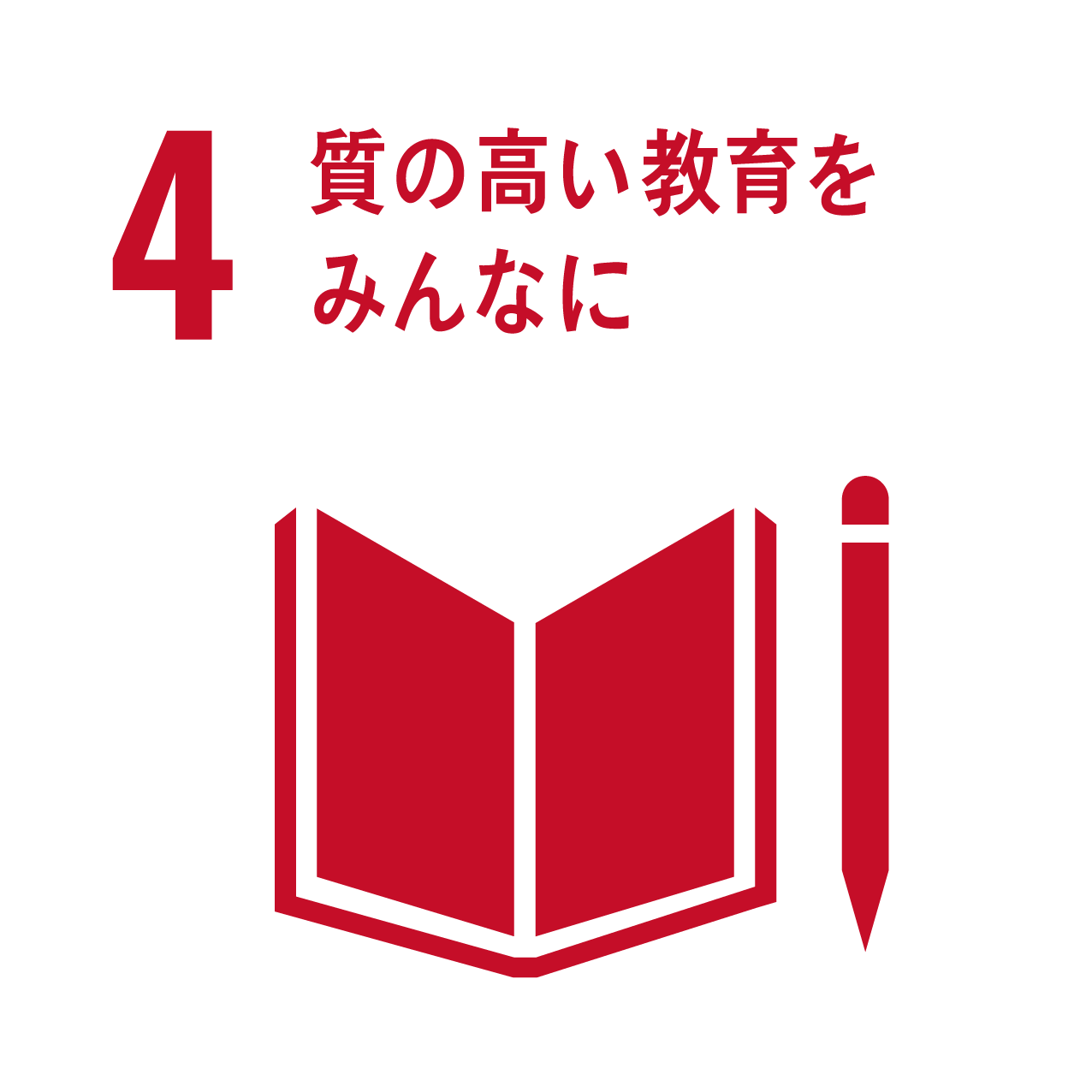
「質の高い教育をみんなに」
武田 晃治 先生
教職課程
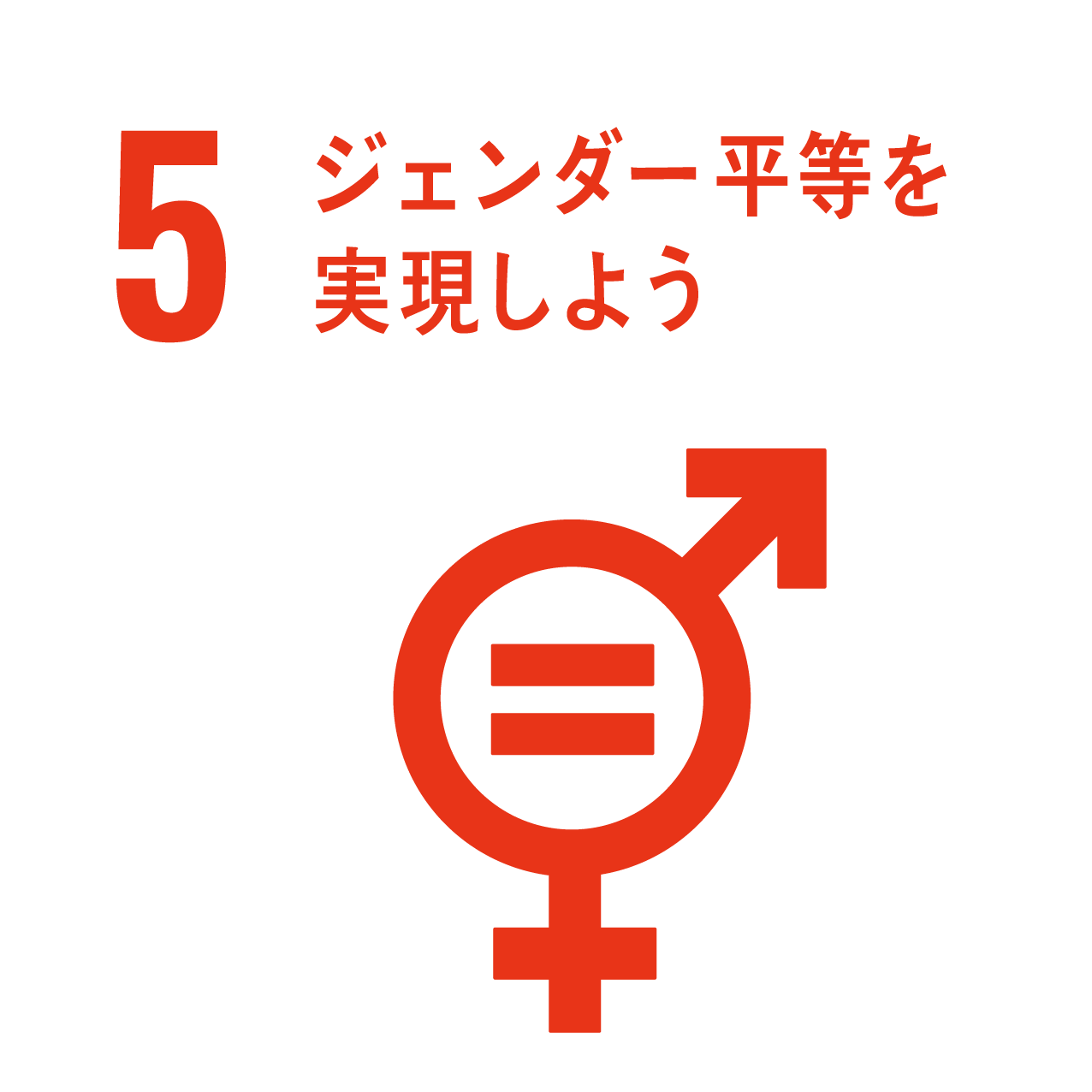
「ジェンダー平等を実現しよう」
原 珠里 先生
国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」
藤本 尚志 先生
応用生物科学部 醸造科学科
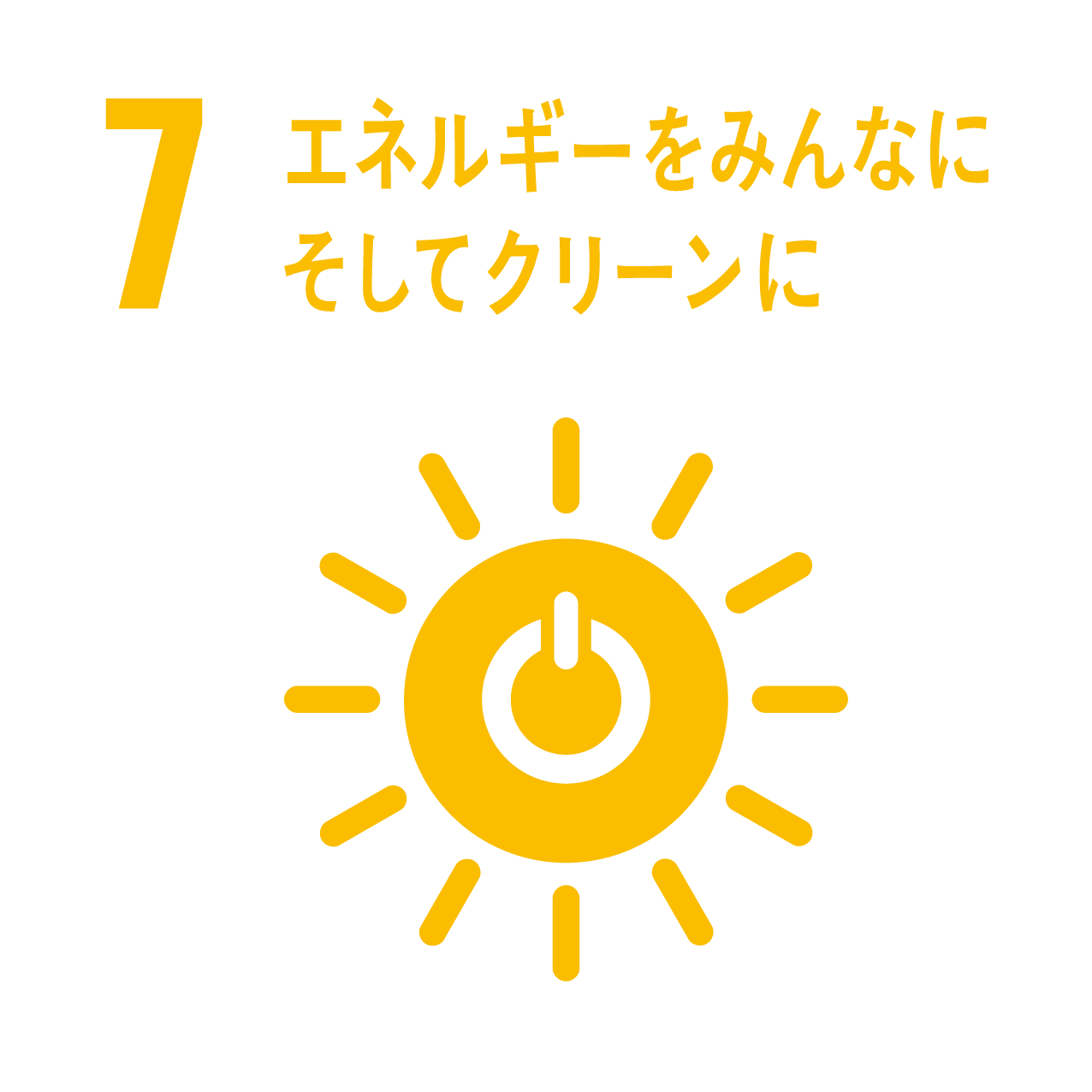
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
トウ ナロン 先生
地域環境科学部 生産環境工学科
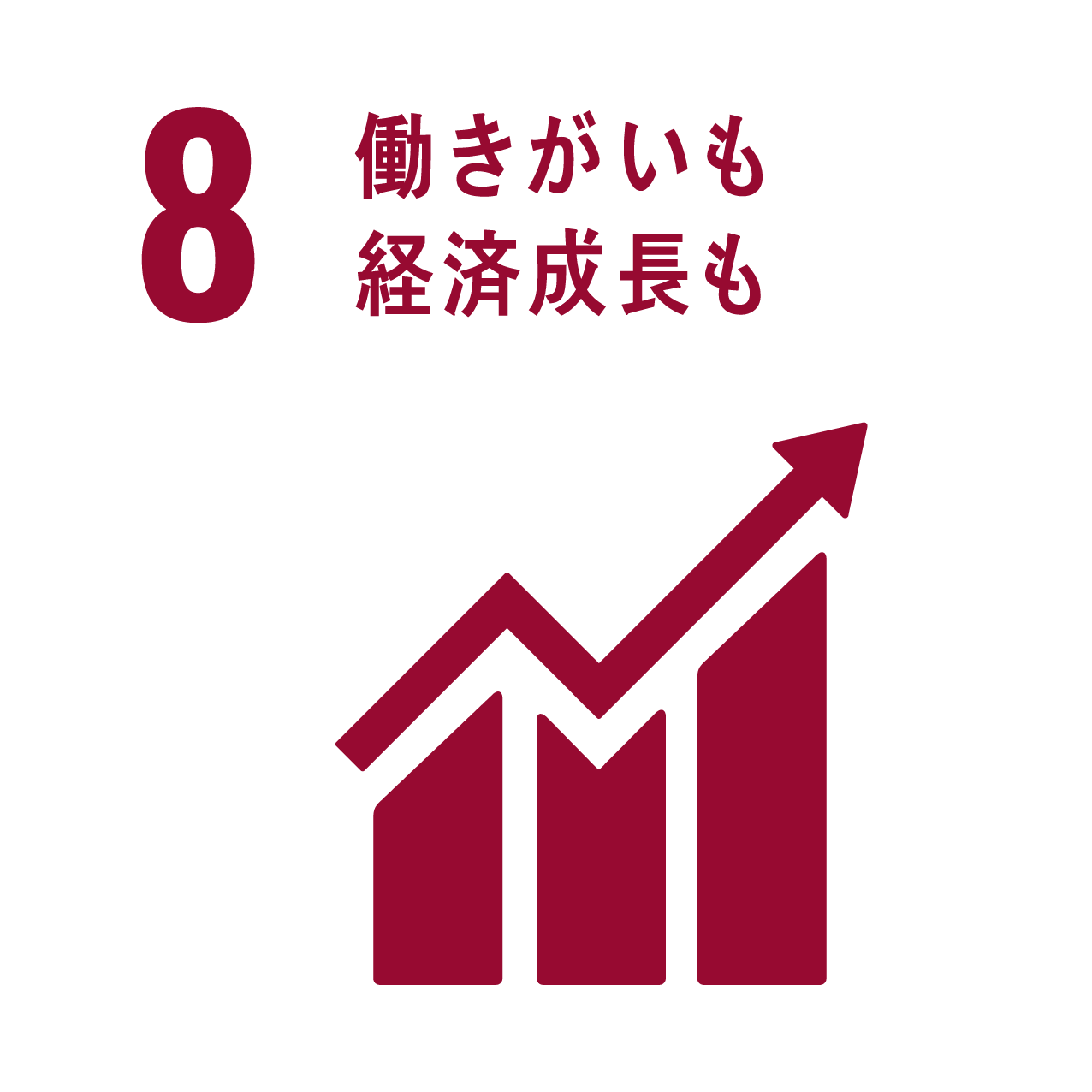
「働きがいも経済成長も」
寺野 梨香 先生
国際食料情報学部 アグリビジネス学科
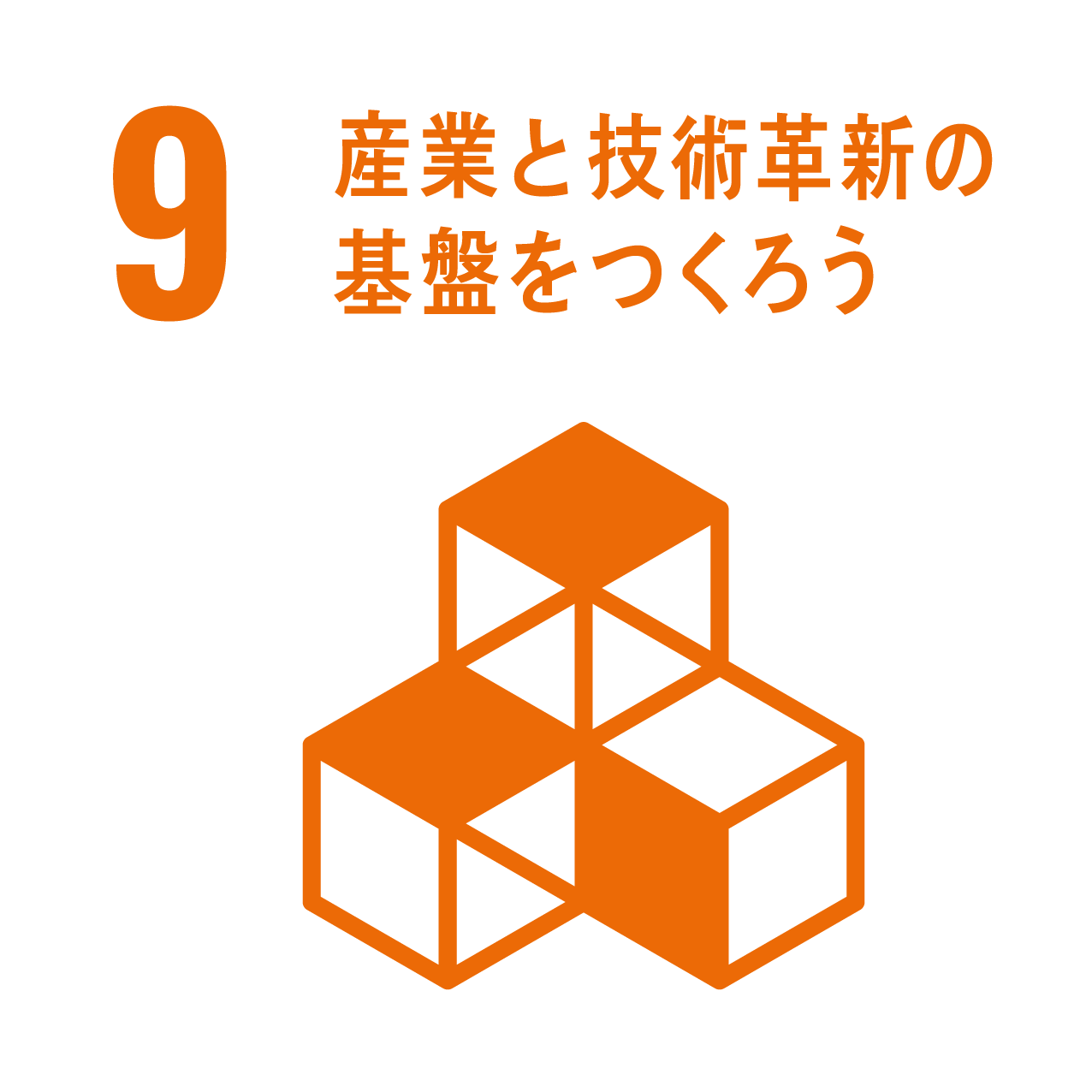
「産業と技術革新の基盤をつくろう」
石井 大輔 先生
生命科学部 分子生命化学科
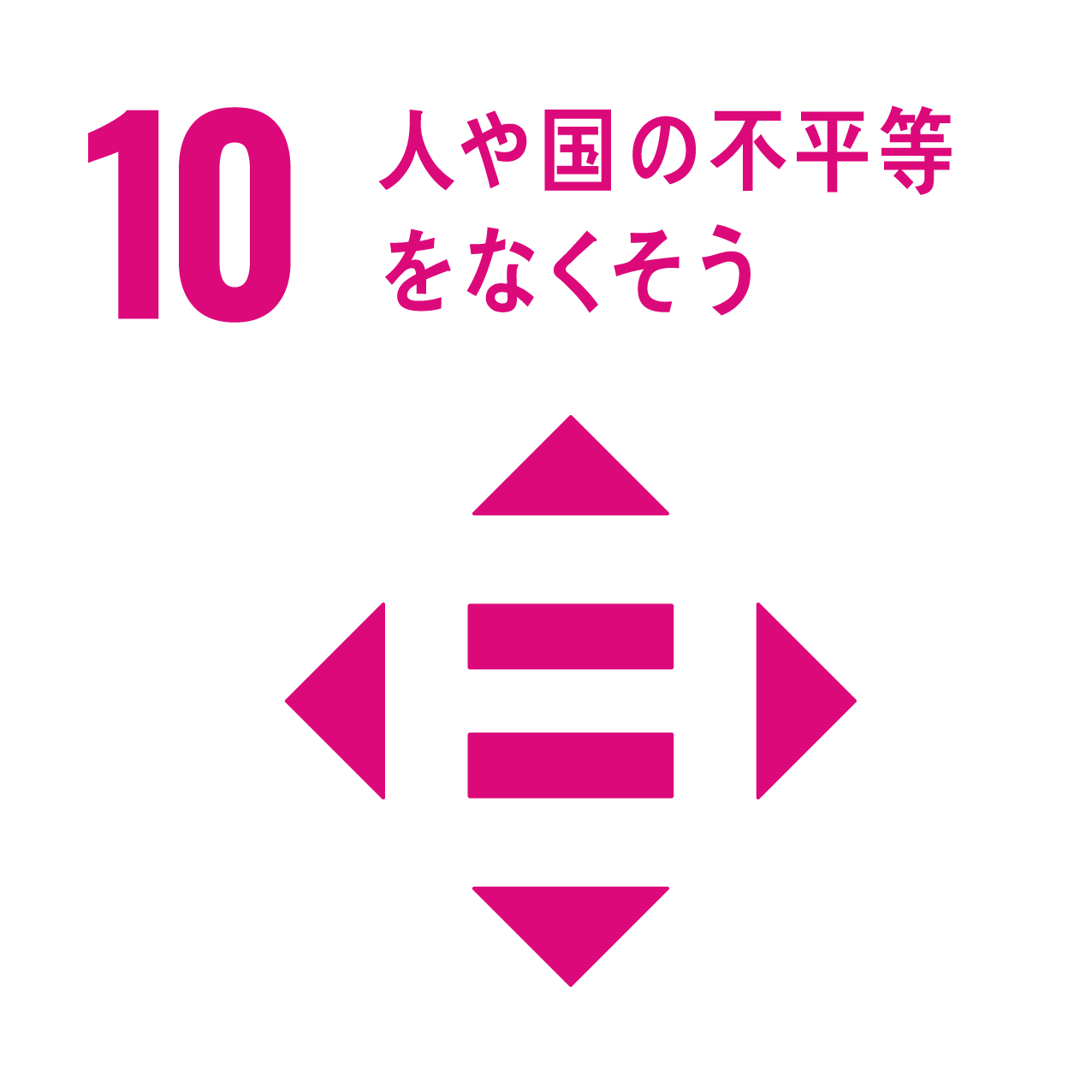
「人や国の不平等をなくそう」
五野 日路子 先生
国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」
山田 晋 先生
農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」
野々村 真希 先生
国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」
太治 輝昭 先生
生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」
中川至純 先生
生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」
入江 彰昭 先生
地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」
佐藤史郎先生
生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」
増田 宏司 先生
農学部 動物科学科