ブレッドフルーツ(BF)の有効利用と新規加工品開発による住民の生計向上と健康改善
”杉原 たまえ 先生
国際食料情報学部 国際農業開発学科


杉原 たまえ 先生
国際食料情報学部 国際農業開発学科
”ブレッドフルーツ(BF)の有効利用と新規加工品開発による住民の生計向上と健康改善
”ブレッドフルーツ(BF)の有効利用と新規加工品開発による住民の生計向上と健康改善
”国際食料情報学部 国際農業開発学科


国際食料情報学部 国際農業開発学科
”ブレッドフルーツ(BF)の有効利用と新規加工品開発による住民の生計向上と健康改善
”
(2021年11月 取材)
かつてハワイ大学に留学した際、貧困に窮するネイティブハワイアンの多くの家庭でブレッドフルーツが植えられていることに関心をもちました。この植物は、ネイティブハワイアンのみならず、太平洋島嶼国やカリビアンの国々では主食のように用いられてきた、彼らのアイデンティティーにつながる重要な植物です。
近年、太平洋島嶼国では調理が簡便で高カロリーの食品が輸入されるようになった結果、ブレッドフルーツ、ココナツ、タロイモなど伝統的食用作物の利用が減退する一方で、輸入食品の過剰摂取によって糖尿病などの生活習慣病が増えるなど、健康問題や生計悪化問題が深刻化しています。
私が注目したブレッドフルーツは、収穫時期が集中することと保存性が低いため、収穫された果実が大量に廃棄されていました。一方この頃から、ブレッドフルーツには肥満や糖尿病患者に有益な栄養機能が備わっているという知見も明らかにされつつありました。そこで、このブレッドフルーツという重要な伝統的食用資源に着目し、南太平洋のトンガ王国の人々と協働して、有効利用の促進や廃棄量を減らすための加工品開発などに取り組み、住民の健康や生計の改善に寄与したいと考えました。
このような問題意識のもとに、JICA草の根技術協力事業に応募し、その採択をうけて2017年3月からトンガ王国で「ブレッドフルーツ(BF)の有効利用と新規加工品開発による住民の生計向上と健康改善」のプロジェクトをスタートさせました。
このブレッドフルーツのプロジェクトで追及しているテーマは、①苗木の増殖技術、②コミュニティーへの苗木提供、③剪定技術、④収穫用具の改良とポストハーベスト技術、⑤新規加工品開発(冷凍・粉など)、⑥栄養・機能性分析、⑦コミュニティーでの啓発活動、⑧諸活動を実現するための社会・経済的条件の分析など、広範囲に及びます。このため、様々な分野の専門家に加わっていただき、チームを結成しました。豊原秀和教授(熱帯作物学)、野口智弘教授(食品加工)、石田裕教授・谷岡由梨准教授(栄養学)、田島淳教授(生産工学)、岩本純明教授(農業経済学)、そしてプロジェクトマネージャーである杉原(農村開発社会学)の7人です。またトンガ側のカウンターパートとして、精力的なコミュニティー支援活動を展開している現地NGOと社会貢献に積極的な民間企業の参加を得ました。
現地活動に際して私たちが最も注意している点は、現地の人々のニーズを第一として活動することです。たとえば、必要だからという理由で高度な食品加工機械を持ち込んでも、それが壊れてしまえば現地では修理できず、活動はストップしてしまいます。そうしたことが起こらないように、「先進技術」優先ではなく、その国に合った技術(「適正技術」)の採用を重視し、プロジェクト終了後は現地の人々だけで活動を継続していけるように配慮しています。農大チーム、現地NGO、現地民間企業という3者で形作られる三角形の真ん中には、常にトンガのコミュニティーの人々が存在するように活動しています。トンガのみなさんから多くのことを学ばせていただいていることに感謝しつつ、コミュニティーを取り残した身勝手なプロジェクトには、絶対にしてはいけないと思っています。

このプロジェクトは、SDGsに多岐にわたって貢献しています。ブレッドフルーツは大量の実をつけますが、収穫が短期間に集中するうえ保存性が低いため、収穫物の多くが消費しきれず無駄にされてきました。そこで私たちは、ブレッドフルーツを冷凍や粉に加工することで、伝統的食用資源が新しい機能性食品となり得るような有効利用を目指しました(「SDGs 12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する」)。また加工品が開発できれば、輸入食糧に代替することで食料自給率を高めることができますし、新たな所得源を生み出すことで住民の生計改善にも寄与できると考えました。この点で、「SDGs 1 貧困をなくそう」に貢献しています。
加工品の製造・販売によって農村女性や若者への新規就業機会を生み出す効果が期待できます。この点では、「SDGs 5 ジェンダー平等を実現しよう」や「SDGs 8 働きがいも経済成長も」にも貢献しています。
ブレッドフルーツ粉はグルテンを含まないので、グルテンアレルギーに悩む人たちの食品として期待できます。また、食物繊維を多く含み、水分吸収率が極めて高く満腹感を与えるため、肥満防止や糖尿病対策の食品として有望です。この点では、「SDGs 3 すべての人に健康と福祉を」に貢献できます。
近年は気候変動により太平洋島嶼国では、海面上昇やサイクロン被害の脅威が高まっています。ブレッドフルーツは耐塩性が高く粗放栽培に適しているので、気候変動にも適用度の高い作物と評価できます。また、加工品開発により長期保存が可能となるため、災害時のフードセキュリティー機能も果たします。この点で、「SDGs 13 気象変動に具体的な対策を」に貢献できます。
本プロジェクトでは、現地カウンターパートがブレッドフルーツの苗木を増殖してコミュニティーに配布していますが、苗木を植える際には、果樹と作物を混作する伝統的な「アグロフォレストリー」として展開するよう心がけています。この点で、「SDGs 15 陸の豊かさも守ろう」に貢献します。
こうした一連の活動は、トンガ側のカウンターパートとなるNGOや社会貢献活動に積極的な民間企業、および東京農業大学との3者の連携によって進められており、「SDGs 17 パートナーシップで目標を達成しよう」を実践していると言えるでしょう。
本プロジェクトは5年目に入りましたが、第1次産業(農業・水産業)と第3次産業(サービス・公務)に偏ったトンガの産業構造に対して、初めて本格的な製造業(第2次産業)を導入するきっかけとなりました。新規加工品開発した生産物は国内およびオーストラリアやニュージーランドなど海外に向けて販売を始めています。海外市場をターゲットとした農産物加工は、トンガでは初めての経験でしたが、私たちのプロジェクトの成果が広く報道されたことによって、トンガ国内での農産物加工への関心が大いに高まりました。トンガ政府も農産物加工を重視するようになりつつあります。
こうしたブレッドフルーツの多角的利用をエントリーポイントとして、トンガのみなさんが主体的にこれからを選択していくことが何より大切だと思います。私たちは、種を播き、それが根を張るお手伝いを少しさせていただき、そのあとは完全にフェイドアウトすることを目標としています。
このプロジェクトで開発された「Breadfruit Flour」は、グルテンフリーであることに加えて、食物繊維が豊富で有用なミネラル類も多く含んでいます。このため、「健康食品」としての評価が高まりつつあり、ニュージーランドやオーストラリアへの輸出も始まりました。

現地カウンターパートは、様々なイベントに積極的に参加し、本プロジェクトで生み出されたブレッドフルーツの加工品を展示・販売するとともに、ブレッドフルーツの重要性を訴え、その有効利用を促す啓発活動に取り組んでいます。

本プロジェクトでは、多様な専門分野からメンバーが参加し、緊密な連携の下で活動を展開しています。

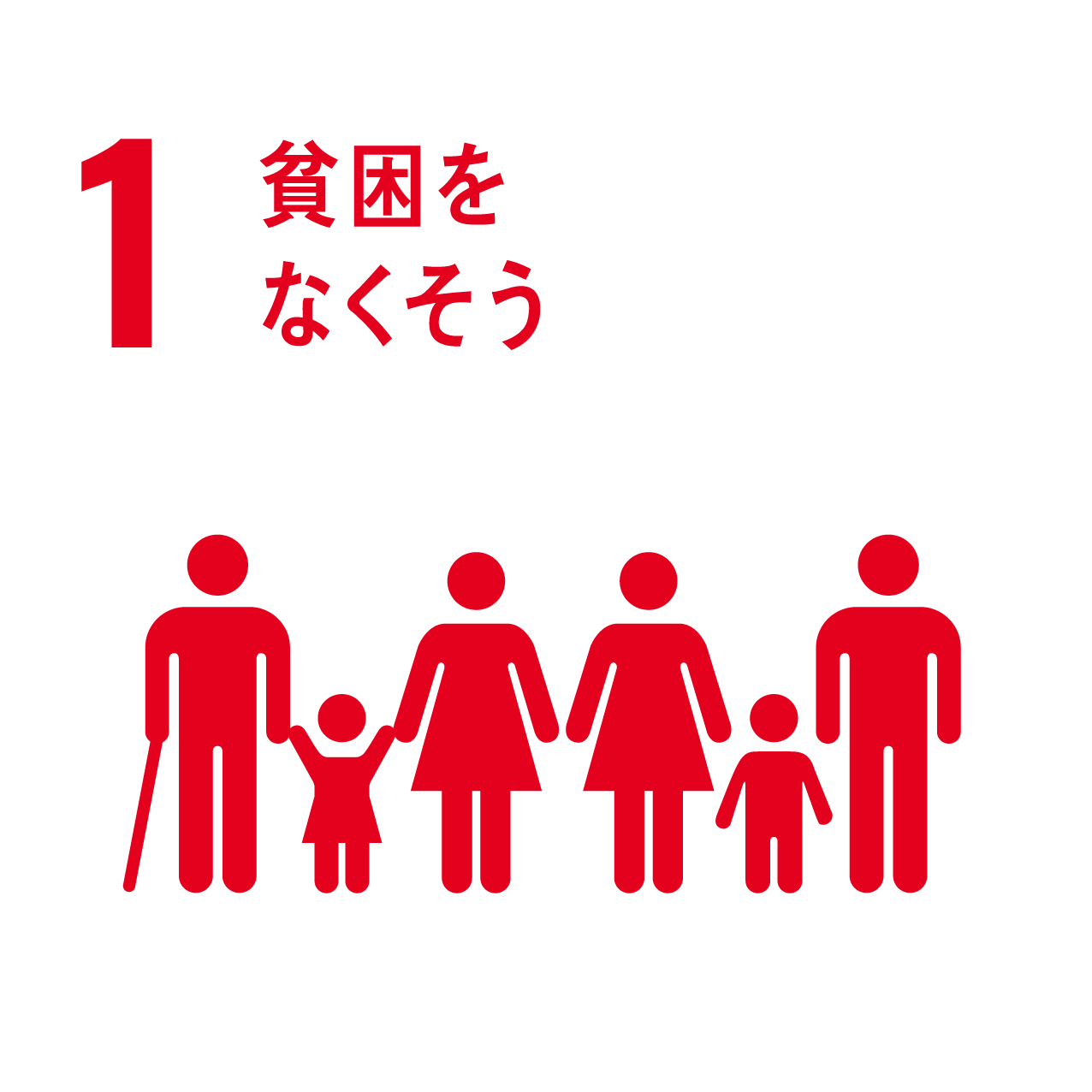
「貧困をなくそう」
杉原 たまえ 先生
国際食料情報学部
国際農業開発学科

「飢餓をゼロに」
松田 浩敬 先生
農学部 デザイン農学科

「すべての人に健康と福祉を」
勝間田 真一 先生
応用生物科学部 栄養科学科
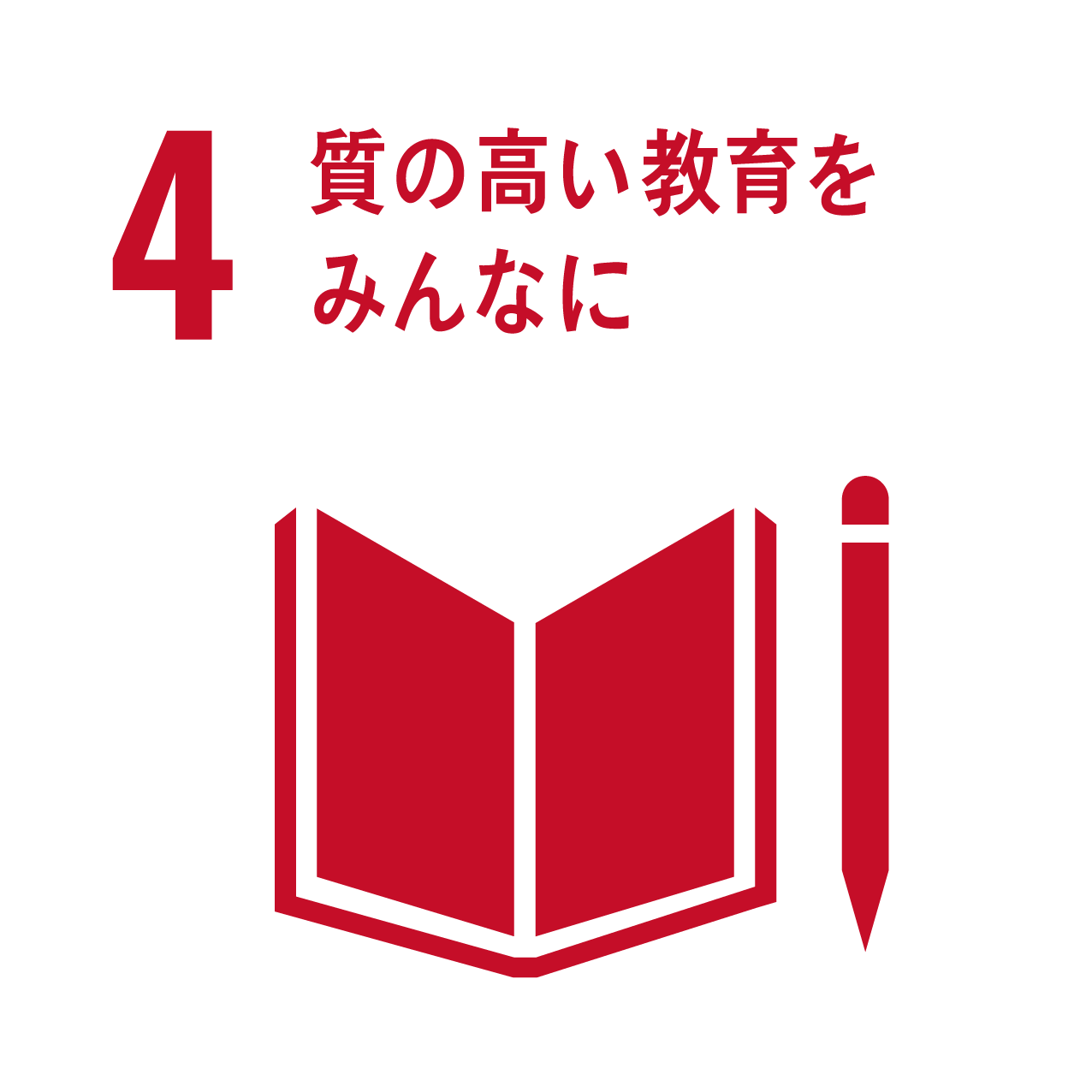
「質の高い教育をみんなに」
武田 晃治 先生
教職課程
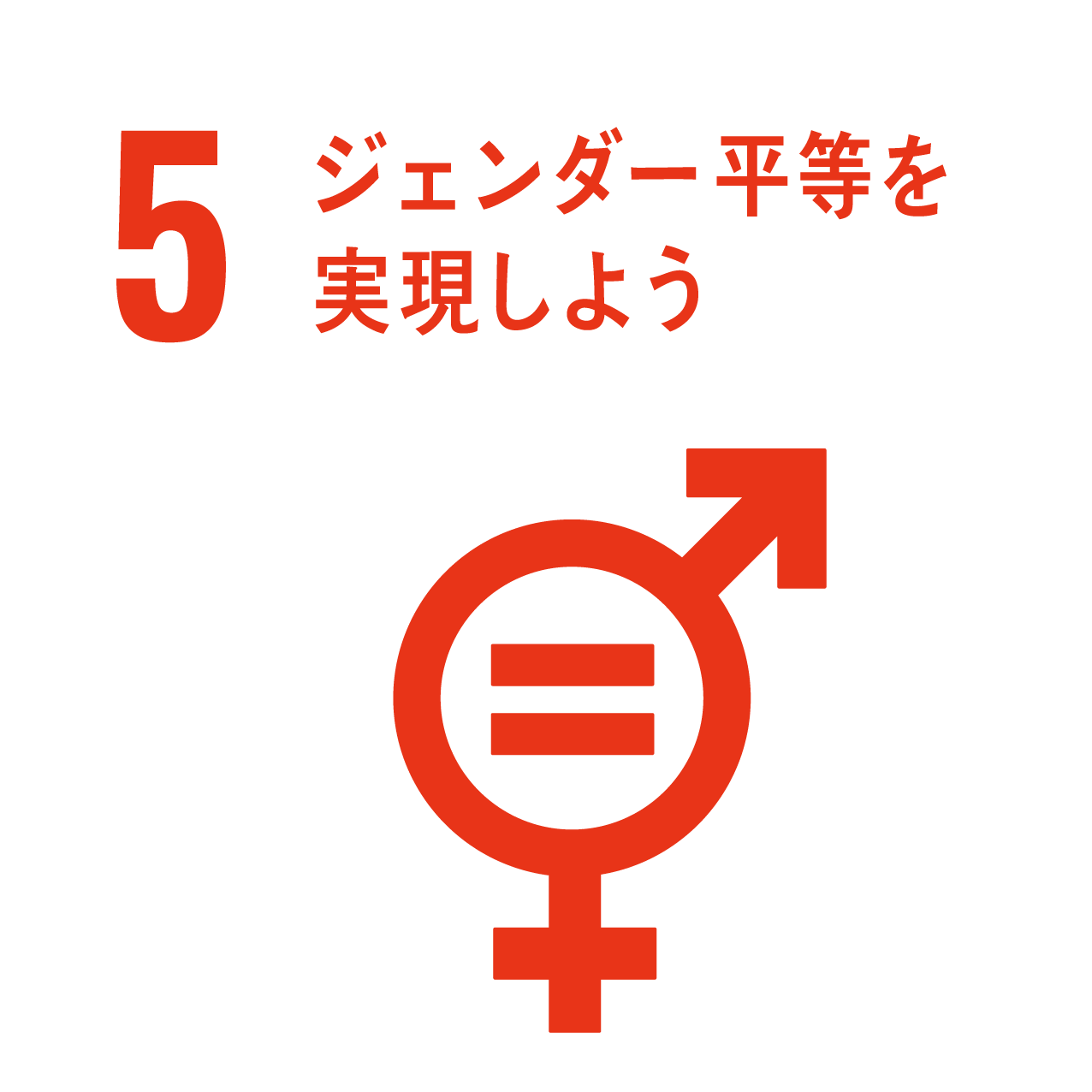
「ジェンダー平等を実現しよう」
原 珠里 先生
国際食料情報学部 国際食農科学科

「安全な水とトイレを世界中に」
藤本 尚志 先生
応用生物科学部 醸造科学科
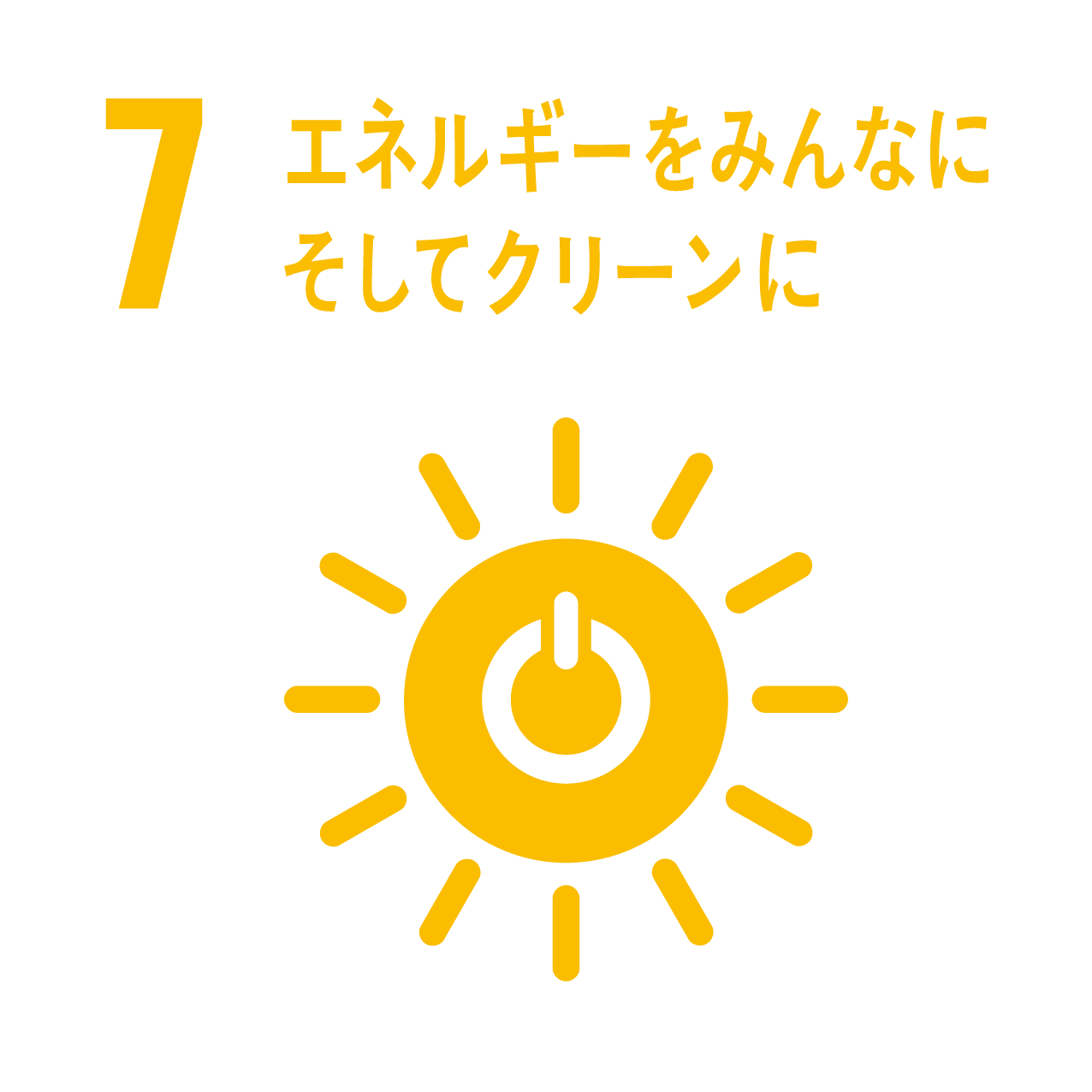
「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
トウ ナロン 先生
地域環境科学部 生産環境工学科
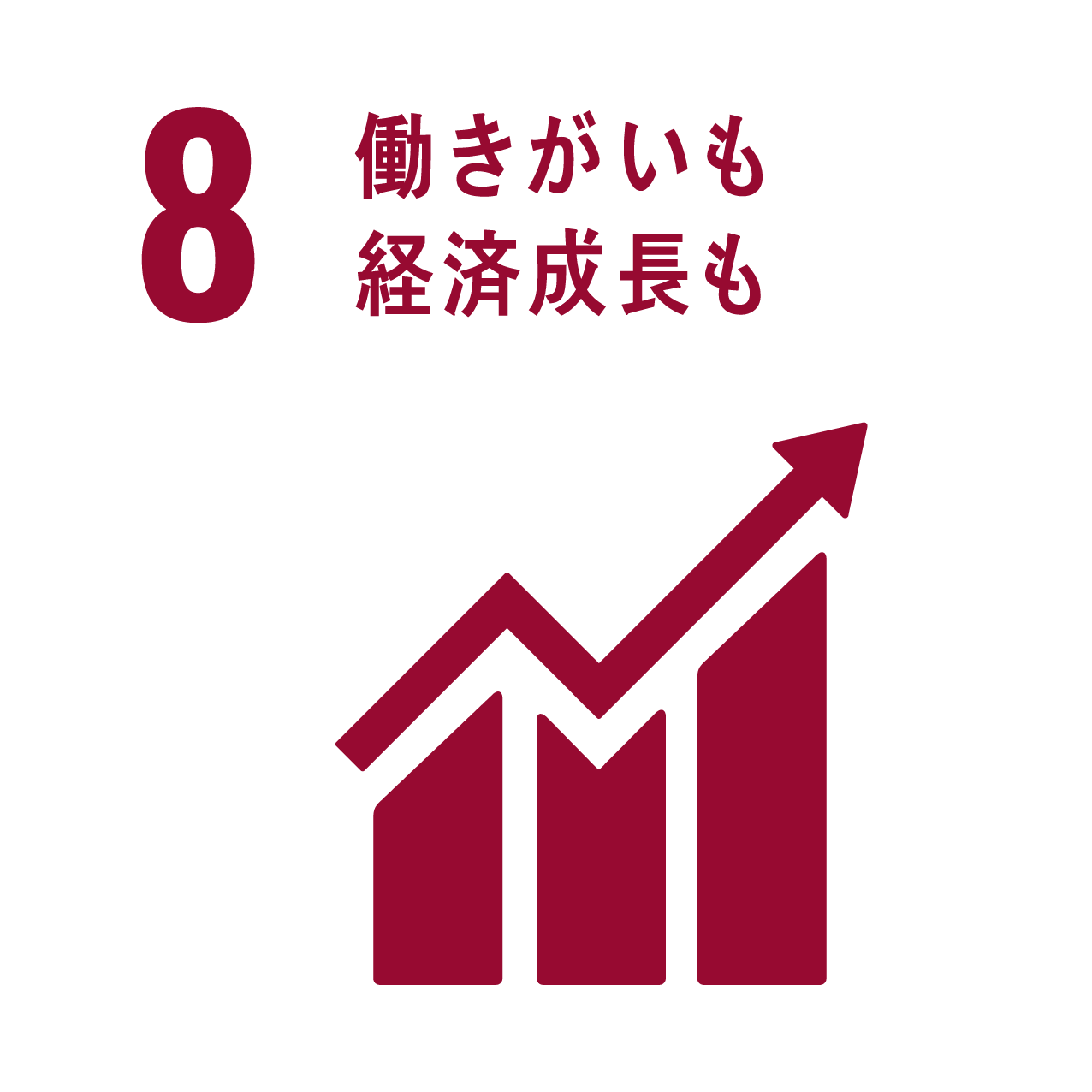
「働きがいも経済成長も」
寺野 梨香 先生
国際食料情報学部 アグリビジネス学科
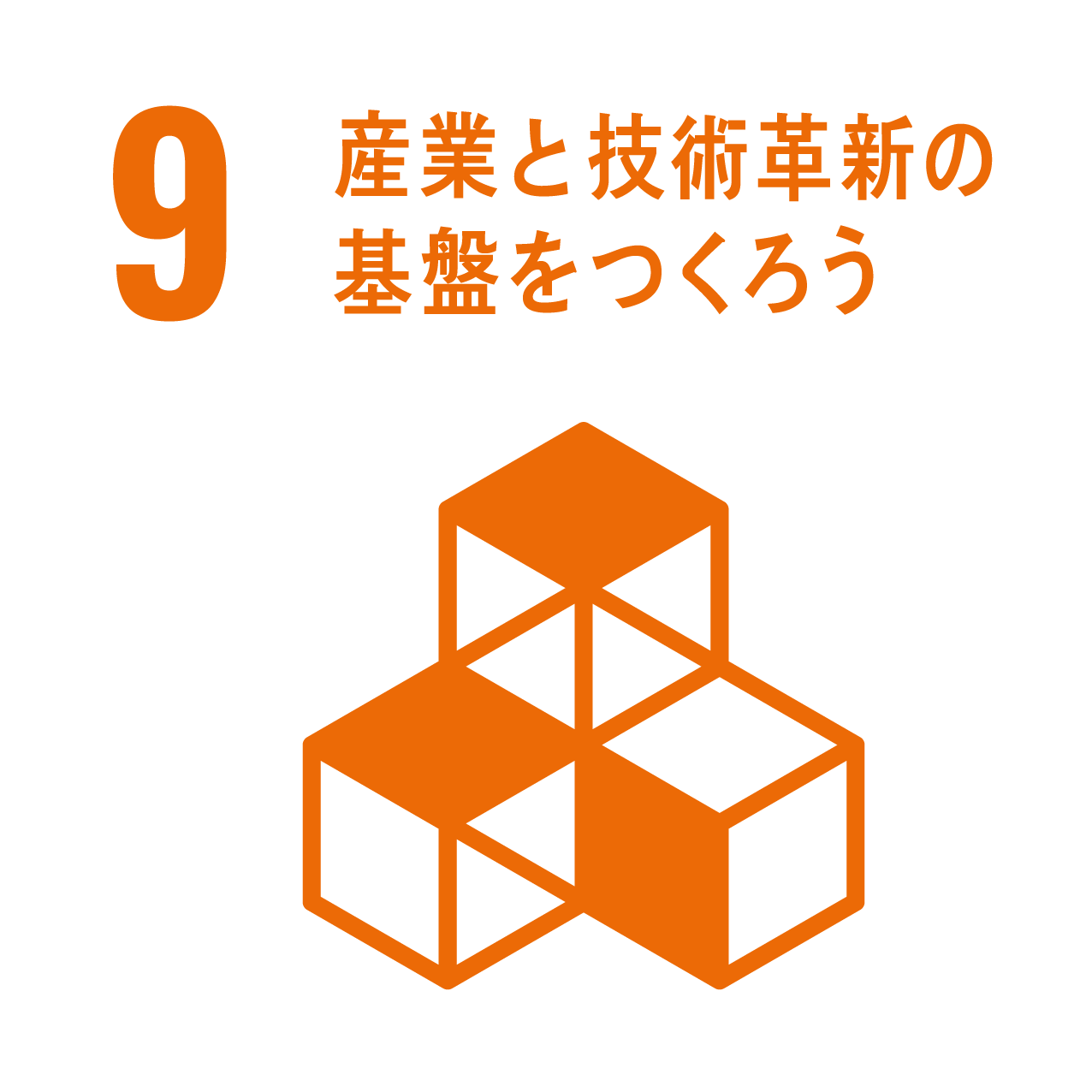
「産業と技術革新の基盤をつくろう」
石井 大輔 先生
生命科学部 分子生命化学科
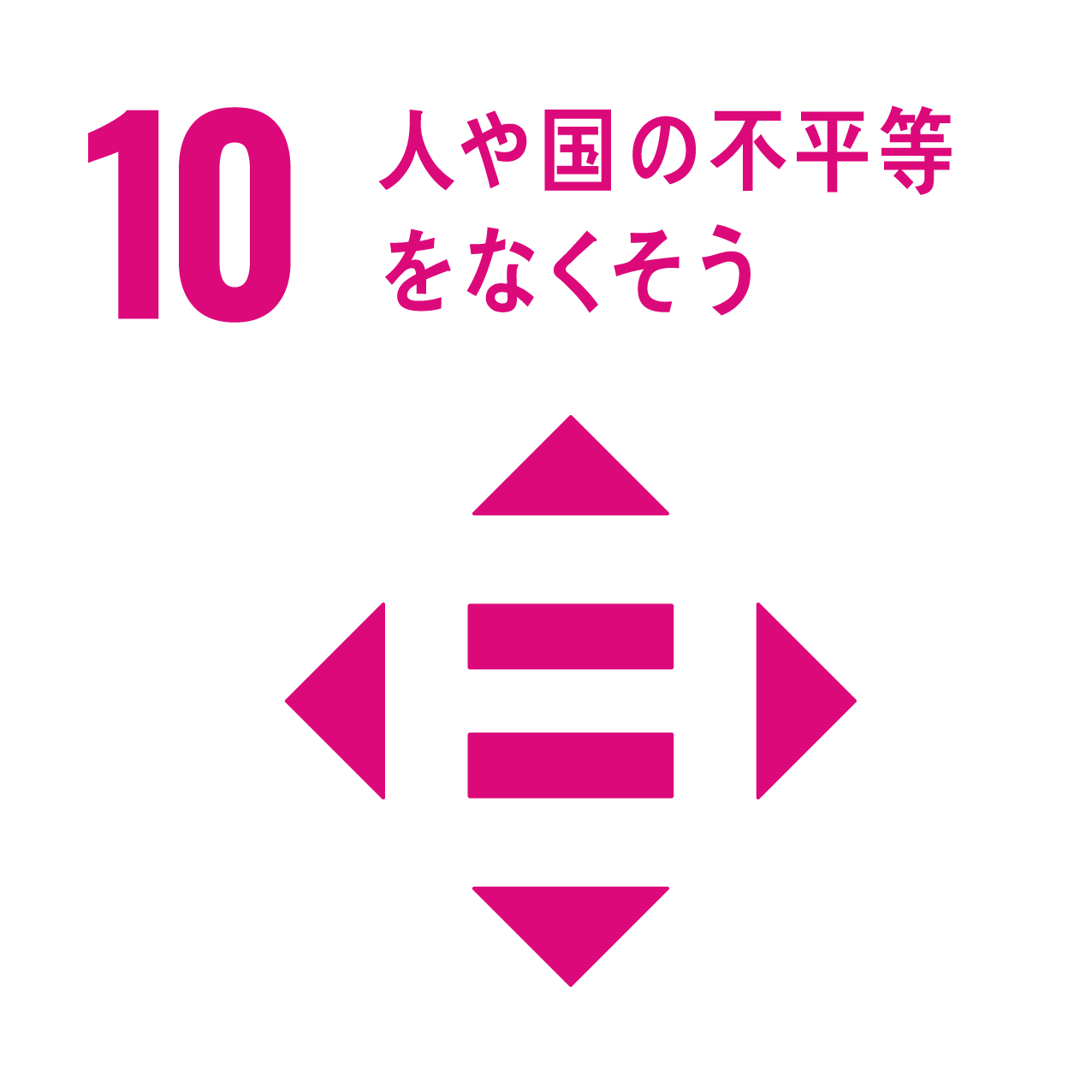
「人や国の不平等をなくそう」
五野 日路子 先生
国際食料情報学部 国際農業開発学科

「住み続けられるまちづくりを」
山田 晋 先生
農学部 生物資源開発学科

「つくる責任 つかう責任」
野々村 真希 先生
国際食料情報学部 食料環境経済学科

「気候変動に具体的な対策を」
太治 輝昭 先生
生命科学部 バイオサイエンス学科

「海の豊かさを守ろう」
中川至純 先生
生物産業学部 海洋水産学科

「陸の豊かさも守ろう」
入江 彰昭 先生
地域環境科学部 地域創成科学科

「平和と公正をすべての人に」
佐藤史郎先生
生物産業学部

「パートナーシップで目標を達成しよう」
増田 宏司 先生
農学部 動物科学科